
「G1地域会議」は、G1メンバーと地域のリーダーたちが、つながり、学び、行動するコミュニティを組成します。

「G1地域会議」は、G1メンバーと地域のリーダーたちが、つながり、学び、行動するコミュニティを組成します。
| 日時 | 2023年09月23日(土・祝) |
|---|---|
| 対象者 | 主に中国・四国地域の発展を担う企業経営者、政治家・官僚、学者・知識人・文化人、メディア等の方(完全招待制) |
| 主催 | 一般社団法人G1 |
現職の総理大臣を始め歴史的に近代日本を牽引した数多くのリーダーを産み出してきた中国・四国地方。瀬戸内海を挟み、日本の多面的な歴史と文化、自然環境が交錯するこの地域はこれからの時代にどのような未来を描くのか。G1に集う地域のリーダーたちが、政治、経済、自然環境、歴史、文化など多角的な視点からその未来像を描き出す。
住民が、共通の要求達成や問題解決のために政府や自治体などに対して行動する「住民運動」。高度経済成長期における公害反対運動や日照権を問題にしたマンション建設反対運動などその歴史は古い。近年、国政選挙の投票率が50%程度で低迷し続け、自治体選挙に至っては30%を切ることも稀ではない状況の中で、市民・国民はいかにして自らの権利を守り、政治・行政といかなる関係を構築していけばよいのか。住民の生活に密着した行政課題を取り扱う、民主主義の最前線ともいえる基礎自治体の現場ではいったい何が起きているのか。社会課題の解決に向けた新たなアプローチや戦略、新たな時代の民主主義の在り方を議論する。
新たな価値を産み出し、雇用を創造する企業の経営力は、地方都市の発展の鍵を握るに与える影響は極めて大きい。各地方都市はなるべく多くの魅力的な企業に我が町に来てほしいと切望している。企業から求められる都市の特性とはいかなるもので、地域を発展させる力を持つ経営者たちは、何を求め、地域の発展をどのように捉えているのか。地域の発展の鍵を握る経営者たちの戦略とビジョンを引き出し、企業と地域の新たな関係性を探る。
デジタルテクノロジー、デザイン思考、そしてダイバーシティー。これら三つの要素が地方における新たなコミュニティ戦略の鍵となっている。実際、三豊では移住者やITを使ったプロジェクトが数多く生まれ、メタバース観光で有名となった男木島でも移住者が島の3分の1以上となっているという。人々のライフスタイルが多様化する新たな時代に価値の高いコミュニティを形成していくにはどのような戦略と手法が求められるのか。新たな時代におけるコミュニティ戦略の最新動向と可能性を探る。
過疎化が進んでいた島根県海士町で、廃校寸前だった島唯一の高校を「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」により立て直し、それを機に人口の流出が転入増加へと反転、Uターンや教育移住者が増えたことで地域の持続可能性の向上につなげた岩本悠氏。NPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラムや子どもたちに学びの場の提供、経済的事情を抱える家庭に対するオンライン学習支援やメタバースを活用した不登校支援などさまざまな教育活動に取り組む今村久美氏。社会の変化により多様化する教育の変革に挑むリーダーたちのリアルに迫る。
テクノロジーの発展でメディアが一気に多様化し、TVerの好調で苦境に立たされるローカル局が多い中、地方メディアには「地域メディアとしての存在意義」が問われている。彼らの間では今何が課題になっており、生き残るためにどのような戦略を講じようとしているのか。これからの地方メディアを考える。
地方都市に開発拠点を持ち、地方都市からクリエイティブな仕事とプロダクトを産み出している経営者や、地方都市を発祥の地とし、全国に生産拠点を展開する経営者がいる。彼らはどのような理由で地方都市でものづくりを行い、ものづくりの未来をどう考えているのか。ものづくり×地方都市の未来を探る。
世界一の日本庭園といわれる「足立美術館」や日本を代表するパワースポット「出雲大社」など、中国・四国地方には世界に誇る歴史的な名所や美しい自然、観光資源が豊富に存在する。これをいかにして、世界レベルの魅力に高め、これから本格的に復活していくインバウンドを掴むことが出来るのか。その戦略と可能性を深堀りする。
令和における町起こしとは?その最前線ではどのような挑戦と革新が行われているのか?伝統的な祭りから公共交通の再生、地域産品のブランド化、DXの活用など、地域の未来を切り拓く、地方創生の最新戦略に迫る。
人口流出傾向が続く地方都市においても、独自の戦略と手法で住民の移住を実現したいくつもの成功事例が存在する。テクノロジーの進化と人々の価値観の変化によって働き方が大いに多様化した今、もともと魅力ある田舎暮らしが出来る地方が移住・定住の選択肢になる可能性は大いに広がってきている。その大きな鍵となるのが、ウェルビーイングだ。暮らす人の、働く人の、地域のウェルビーイングを高めるには何が必要なのか。その具体的な戦略を議論する。
島根県出雲市のCDO補佐官を務めるモンスターラボ鮄川宏樹氏、広島・瀬戸内地方で世界初の人工流れ星プロジェクトを計画していた岡島 礼奈氏、全国に先駆けてスタートアップ都市として起業支援続ける福岡市長髙島 宗一郎氏、広島県で起業し、DXを推し進める吉村 公孝氏。気鋭の起業家や首長たちは、スタートアップと地方の関係をどう捉え、地方に何を求め、何を還元しようとしているのか。スタートアップが切り拓く地方経済の未来を考える。
様々な課題に直面する日本の農林業は、テクノロジーによってどう変わろうとしているのか。地域を盛り上げ持続可能な社会を構築するうえで、農林業は極めて重要な役割を果たす。農林業の現場の最新動向から、持続可能な未来を実現するための新たなアプローチを考える。
近代化から取り残され過疎化が進んだ島々がアートやテクノロジーで復活し、世界的ブランドとなった瀬戸内(SETOUCHI)を始め、日本には本来世界に誇る文化的ブランドが数多く存在する。アート、音楽、食文化、歴史、伝統工芸といった多彩な文化的資源のブランド力を高め、グローバルに発信するにはいかなる戦略が必要か。最新事例を紐解きながら日本の多彩な地域ブランドの可能性とその未来を考える。
「日本書紀」の国譲り神話に記された出雲大社。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の愛した松江。近代日本のリーダーを多く輩出した土佐や長州など、我が国の歴史上無くてはならない役割を果たしてきた中国・四国地方。2023年、パンデミック、ロシアによるウクライナ侵略、エネルギー危機や物価高、国内では昨年の安倍元総理の銃撃事件など、なにが起こるかわからない激動の時代に、私たちはこの地域から何を発信すべきか。世界的視点、歴史的視点から未来を考える。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2023年09月23日(土・祝) |
|---|---|
| 参加費 |
主に中国・四国地域の発展を担う企業経営者、政治家・官僚、学者・知識人・文化人、メディア等の方(完全招待制)
|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
今、世界から注目を集める、SETOUCHIを挟む中国・四国地方。世界に目を向ければ米中貿易摩擦などを背景に世界的な景気後退が危ぶまれる中、国内では安倍政権による地方創生政策が根強く続けられた結果、各地域で政治や民間企業による独自の取り組みが進められ、いよいよ真の地域が主役の時代になりつつある。昨年の西日本豪雨災害からも力強く立ち直り、5年連続の経済成長を続けるこの地域は、令和新時代に日本や世界に対して何を発信するのか。
いよいよ宇宙は夢から現実のビジネスのフェーズに移りつつある。かつては国家の威信をかけるプロジェクトであった宇宙も、今や急速なテクノロジーの進化と大胆な投資資金の流入によって、世界中で民間企業、とくにスタートアップによる宇宙ビジネスが続々と産まれている。宇宙というフロンティアに挑む起業家たちの戦略とはいかなるものか。その実像に迫る。
今日ほど企業経営にとってSDGsへの取り組みが重要視される時代はないだろう。世界中の投資家はESG投資を加速し、グローバル化するサプライチェーンの中で顧客からはESGへの対応を求められ、ESGに関心の高いミレニアル世代の消費者の行動は売上に直結する。かつてCSR(企業の社会的責任)とされていた価値観は、マイケル・ポーター教授らが提唱するようにCSV(Creating Shared Value)、すなわち、社会利益と企業利益の共同実現といった、新たな持続可能性時代の企業の競争戦略といった価値観に昇華している。SDGsと経営の最新の議論に迫る。
2018年7月、14府県で260人以上が犠牲になった西日本豪雨は平成最悪の水害となった。なぜこれほど多くの犠牲者が出たのか?生死を分けたのは何だったのか?過去に例を見ない大規模な水害が毎年のように発生する異常気象新時代の日本において、命を守り、郷土を守るためにリーダーが取るべき行動を検証する。
近年、日本においても企業や社会におけるインクルージョンの重要性が益々高まってきている。それはもはや、「そうすべき義務」などではなく、インクルージョンこそが、変革の時代に経営や事業、そして社会を強くし、革新を生み出すという認識が広がってきているのだ。しょうがいを持ちながら社会を変革するリーダーたちから、新たなインクルージョンのかたちを聞き出す。
地域と日本を良くするためにリーダーとして私たちはいかなる行動をすべきか。G1の基本理念(1)批判よりも提案を、(2)思想から行動へ、(3)リーダーとしての自覚、という3つの行動指針に則って自由に議論していただきます。
テクノロジーの急速な進化により、あらゆる分野でビジネス環境は一変し、新たなビジネスモデルの創造がなければ成長できない時代となった。衣食住からレジャー、エンタメ、モビリティまであらゆるビジネス領域に急激に拡大するサブスクリプションモデル。あらゆるものがサービスとして提供される「XaaS(X as a Service)」の時代においてサブスクリプションモデルはいかなる進化を遂げるのか。急激に変化していく時代を勝ち抜く次の一手とは。
いよいよ2020年から商用サービスがスタートする5Gは、単に通信インフラの進化にとどまらず、劇的な構造変化を地方の社会や産業にもたらす可能性が高い。超高速大容量・低遅延・同時多接続を特徴とする5Gは、これまでの100倍の速度、1000倍の容量でIoTを実現する。地域のトップランナーたちは、地方創生の文脈においてこの破壊的変化をもたらすインフラにいかなる可能性を見出しているのか。その戦略に迫る。
農業分野で意欲的な取り組みを進めるパイオニアの多い中国地方。ワインの名産地フランス・ローヌ地方コルナスで約20年腕を磨き、岡山市で自然派ワイン造りを進める大岡弘武氏、耕作放棄地再生を目的にtetta株式会社を設立し、tettaワインのブランドを築いた高橋竜太氏、独自の耐寒性遺伝子情報覚醒技術を開発し、該当植物がより低気温な場所でも栽培に適するように変異させた耐寒性植物を展開する田中哲也氏、瀬戸内の島で四季折々の果実を使い、この島でしかできない高品質なジャム造りに取組む松嶋匡史氏、第一線を進むパイオニアたちに見えている食・農・地域の未来とは。
ラグビー、バレー、バスケットボールなど、この夏、ワールドカップで世界を相手に大いなる活躍を見せて国中を沸かせた日本のスポーツ界。現代におけるスポーツの持つ広範な価値を最大限に活かし、経済的・社会的なベネフィットを最大化するにはいかなる視点が必要なのか。2020東京五輪も開催間近となる中、スポーツビジネスの今後の展開を探る。
MaaS、ドローン、VR/AR、AI、IoTなどテクノロジーの急速な発展は、高齢化や過疎化といった課題を抱える地域のモビリティを劇的に変える可能性を持つ。むしろ、過疎化した地域が、人口の密集した都市部ではできない先進的な取り組みを進めるフロンティアにもなり得るといえる。これからの「移動」はどのように進化していくのか。その展望を探る。
人口減少・超高齢化といった課題に直面する日本で政府が地方創生の旗を振り、取り組みを進める中、町おこしにおいて地銀が果たす役割に大きな期待が寄せられている。地銀の持つ目利き力、人材、ネットワークや地域特性に応じたコンサルティング能力などを活用することで、地方の社会・経済を成長させるための方策とはいかなるものか。第一線で活躍するリーダーたちの議論から町おこしのチャレンジに迫る。
イノベーションは辺境の地から始まる──。日本最小の人口である鳥取県・島根県等で、中山間地域の活性化や地域創生に向けた取り組みが進展している。そのカギを握るのが林業だ。先進地である智頭町の事例を題材にしながら、これまで遠い存在であった広大な森林(日本列島の67%)を、いかに地域の経済と暮らしに取り戻し、持続可能な地域強化につなげるのか議論する。
テクノロジーの進化は社会や産業の構造を加速度的に変化させ、もはや「昔はこうだった」といった常識や前例はほとんど通用しない時代となった。予測不能な時代となった新たな時代を生き抜く大人を育てるために必要な教育の在り方とはいかなるものか。翌年に迫った2020年教育改革において大学入試への英語民間試験導入が急遽延期に転じるなど、国の政策が迷走を見せる中、教育界のリーダーたちが教育の今と未来を語る。
国際的に大きな影響力をもつ『National Geographic Traveller』(UK版)で、The Cool List 2019の1番目に日本で唯一瀬戸内が選定されるなど、「SETOUCHI」に世界から熱い視線が集まっている。そもそも、観光の父と呼ばれたイギリス人実業家トマス・クックが1872(明治5)年に瀬戸内海を訪れた際、その多島海景観が絶賛されている。その後近代化から取り残され過疎化が進んだ島々が、今アートやテクノロジーを起爆剤に復活を遂げたのだ。世界的なブランドとなったSETOUCHIで、リーダーたちが次に目指す指標とは。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2019年11月23日(土) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2015年10月16日(金)〜2015年10月17日(土) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
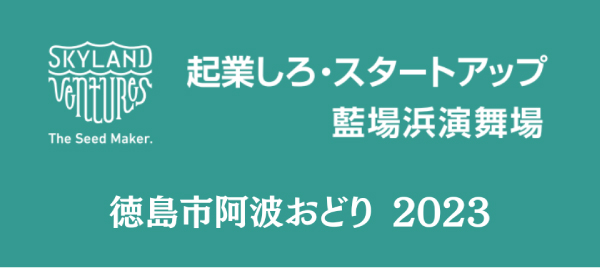




















東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル 株式会社グロービス内
TEL:03-5275-3681
E-Mail:G1region@globis.co.jp