
「G1サミット」は、日本・世界を担っていくリーダーたちが学び、交流し、絆を深め、日本を良くする行動を起こすためのプラットフォームです。

「G1サミット」は、日本・世界を担っていくリーダーたちが学び、交流し、絆を深め、日本を良くする行動を起こすためのプラットフォームです。
世界を覆った新型コロナによるパンデミックもいよいよ出口が見えつつあるのか。オミクロン株流行の中でも各国ではコロナ以前の行動様式へ戻すための行動規制の解禁が進む。一方、ロシアによるウクライナへの侵攻など、国際情勢はかつてないほど緊迫し、戦後構築されてきた国際秩序は変更を迫られている。新たな日本のリーダーとなった岸田文雄総理のもと、我が国はいかなる方向に進むべきなのか。ポストコロナのグランドデザインを議論する。
新型コロナによるパンデミックは、テクノロジーによる社会変容・進化の速度を格段に高める結果となった。いまや人々は新たな技術を積極的に生活に取り入れ、社会を進化させている。その意味でアカデミックセクターが社会において果たす責任の重要性も高まり、変化してきたといえよう。常に進化し続けるテクノロジーの社会実装を通じて、さらに2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、経済はいかなる成長を遂げるのか。密接に絡むアカデミー・テクノロジー・経済の観点からポストコロナの展望を望む。
クリミア半島の併合に続いてウクライナへの侵攻を進めるロシア。国際秩序に平然と変更を加えようとする新興国の実力行使に対して、米国バイデン政権と欧州各国はどのように対抗していくことになるのか。台湾海峡や南シナ海への膨張傾向を隠さない中国と隣接する我が国に、欧州の危機を対岸の火事として見ている余裕はない。複雑さを増すポストコロナの国際情勢のもと、我が国の外交・安全保障のグランドデザインを議論する。
超長期にわたるデフレと低成長に苛まれてきた日本経済。コロナによる社会構造や産業構造の変化を超えて、ポストコロナで世界経済を牽引するような飛躍を遂げるための新たな産業政策とはいかなるものか。岸田内閣が掲げる「新しい資本主義」や「経済安全保障」は日本経済の成長にいかなる貢献をもたらすのか。ポストコロナ時代に日本が取るべき経済政策の方向性を議論する。
昨年9月に発足したデジタル庁。コロナによる社会の変化を追い風に、これまで遅々として進まなかった行政部門のデジタル化を進めることが最大の狙いだ。ハンコ廃止などのスモールサクセスからスタートし、遠隔医療など徐々に規制の壁を乗り越えつつあるようにみえるが、ポストコロナに向けて日本社会のDXはどこまで進展するのか。その課題と展望を議論する。
TwitterやInstagram、YouTubeなど誰もがSNSから多角的に情報を入手し、発信する時代。不祥事や失言をきっかけにした「炎上」や意図的な「フェイクニュース」の蔓延、SNS上の誹謗中傷による自殺など過去には無かった新たな社会現象も頻発する。個人、公人、企業、政府はこうした社会現象とどう向き合い、いかなる姿勢で情報発信を行うべきなのか。メディア、ジャーナリズム、政治、戦略的コミュニケーションなどの観点から、ポストコロナ時代の情報発信のあり方を考える。
介護や福祉、保育や教育の現場など、デジタル化の最後の砦と考えられてきた分野においても、DXによる変革の波が押し寄せつつある。コロナによる社会の構造変化を機に、こどもや福祉の現場ではいかなる変化が起きているのか、そして岸田内閣が創設を決めたこども家庭庁はどのような役割を果たすのか。ポストコロナ時代を見据えてソーシャルセクターとDXの展望を議論する。
コロナによるサプライチェーンの分断は、改めて経営におけるサプライチェーンの重要性を認識させる結果となった。昨年財務省が行った調査でも、ポストコロナに向けて「サプライチェーンの多元化・強靱化」の必要性を挙げる企業が多く、「調達先の多様化」に加えてAIやロボットの活用による「デジタル化」がキーだとする経営者が多い。ウクライナ情勢や米中対立などでグローバルサプライチェーンの地政学的リスクも高まる中、サプライチェーンを強靭化するにはいかなる戦略が必要か。
急速に人々の関心を集めている「メタバース」現在何が出来て、今後いつまでに何ができるようになるのか。そして、新たなテクノロジーは社会にどのような変化をもたらすのか。世界に先駆けてメタバースへの投資を進めるトップランナーたちの議論から、web3.0に移行するこれからの時代を先読みする。
2年にわたるコロナ禍での生活は私たちの価値観を変え、潜在していた社会の諸問題もあらわになった。SNSで双方向で情報を入手し、発信しあうことが当たり前となる中、web上での誹謗中傷に耐えかねて自殺したり、孤独にさいなまれて社会を壊す行動にでる事件も頻発する。苦境にこそ、時代を超え、繰り返し再発見されるものを蓄えてきた宗教の精神が大きな役割を果たす。ポストコロナ時代において、人類は心の問題にどう向き合うべきなのか。
G1メンバーの行動で動き始めた日本の水産改革。水産流通適正化法が施行され、IUU漁業(違法・無報告・無規制な漁業)によって捕獲された水産物が流通しないよう2022末までに漁獲証明書を義務付ける作業が進んでいる。しかし、EUはすでに全魚種を漁獲証明書の対象とし、アメリカでも今年全魚種化に向けて法案が提出されている一方、日本は、国内漁業対象魚3種、輸入魚種4種の合計7種でスタートとなり、クロマグロなど重要魚種に関しては触れられておらず骨抜きの懸念も生じている。日本と世界の水産資源と海洋環境を守り、日本の水産業を再生するために私たちが取るべき行動とは。
コロナによるパンデミックは、世界の金融市場も大きく揺さぶることとなった。一方、コロナ禍でESG投資やインパクト投資が益々進むなどマネーの流れも変化している。世界的なインフレと金利上昇圧力の高まりによって資金調達も投資活動も全て順調だった時代にも終わりが近づいていると指摘されるが、コロナ禍を乗り越えた先の未来はどうなるのか。専門家の立場から見据えるポストコロナ時代のマネーの新潮流を議論する。
日本の大学の引用論文数の減少、世界ランキングの順位低下など、我が国の科学技術競争力の凋落が叫ばれて久しい。科学技術予算は、過去20年間に、米国とドイツが2倍弱、韓国で5倍以上、そして中国は十数倍にも増やしている一方、日本は横ばいだ。ポストコロナ時代、20年以上続く研究力低下に歯止めをかけ、イノベーションを起こし、世界をリードする技術力を再建するために日本が取るべき戦略とはいかなるものか。
昨年末G1に新たなイニシアティブが発足した。「G1あしながイニシアティブ」だ。貧困や虐待に苦しむ全国の子ども達を支援するため、経済界のみならずNPOやアート、スポーツ、教育など多様な領域で活躍するG1メンバーが自分達に出来ることを直接的に支援をすることで、将来的には全国に約600ある児童養護施設の子ども達を物心両面で継続的に支援し、子ども達の進学率の向上に向けた教育面でのサポートも拡充していく考えだ。志のあるメンバーが集うプラットフォームとしてのG1の利点を大いに活用する彼らの行動から、ポストコロナ時代の社会貢献の新たな形を考える。
コロナ危機において私たちは、現場の基礎自治体やNPOの努力にもかかわらず、真に支援を必要とする人々に対して十分な支援が届かないという、現状の制度とシステムの限界を突きつけられた。コロナ危機の教訓を踏まえて我々が克服すべき課題と目指すべき道筋はいかなるものか。貧困支援に取り組んでいるNPOなどと行政が連携し、網の目のように支援のネットワークを張るための仕組みづくりとその方法論まで、具体的に議論を展開する。
パンデミックを経て、テクノロジーの進化と市場の変化はその速度を増し、世界における競争も激しさを増した。GAFAMに限らず国境を越えてビジネスを展開する各国の企業と伍して日本の企業も世界で戦っていくため、経営者はその目線を一段上げ、世界を見据える必要がある。激変する世界で競争に打ち克ち、それぞれの分野で世界No.1を目指していくためのあらゆる戦略を議論する。
コロナ禍は日本が医療提供体制の「病巣」を放置してきた現実を浮き彫りにした。乱立する病院の統合再編は進まず、人口当たりの病床数が世界一多くても、1床当たりの医師や看護師が少ないため、有事の対応が脆弱となった。このため、昨年のコロナ禍では、医療ひっ迫により、搬送先が見つからず救急車が立ち往生する事態が相次いだ。医療界のガバナンス、医療資源の効率的・最適な活用、デジタル化など、これまで聖域だった課題にいかにしてメスをいれていけば、国民の命を守ることができるのか。コロナ危機で露呈した医療の課題の解決に向けた課題と展望を議論する。
パンデミックの渦中で開催された東京2020五輪大会。様々な意見があったが、金メダル27個を含む合計58個のメダルを獲得した日本代表選手たちの活躍に多くの日本人が勇気と感動をもらった。パンデミックという困難の下で開催した東京2020五輪が日本社会と日本人に残したものとは何か。私たちは大会開催を通じて得た知見や経験を今後どのように活かしていくべきなのか。昨夏日本人初のIOCアスリート委員に就任された太田雄貴氏、史上初の金メダルを獲得し大躍進した卓球界を支えるVICTAS松下浩二氏、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会座長をつとめた栗山浩樹氏、そして元ビーチバレー日本代表選手で参議院議員の朝日健太郎氏を交えて、議論する。
多額の寄付金を独自に集め、数兆円規模のファンドを運用してその運用益を研究費や大学運営に充てる欧米のトップ大学と比べて、日本の大学の資金力不足は深刻だ。政府は10兆円の大学ファンドの運用を開始して大学を支援する計画だが、その実現は先の話だ。資金力不足に加え、少子化、学生がリアルで学ぶ機会の減少など、大学を取り巻く環境は厳しさを増す。人材育成は国づくりの基礎となる。その現場である大学経営の現状と課題、そして未来への展望を議論する。
コロナ禍による人々の生活スタイルの変化は、各メディアにどのような影響を与えているのか。実際、自宅で過ごす時間が増加したことに伴い、ネットやテレビ、ラジオといったメディアを利用する機会が増加しているという各種調査の結果が示されている。一方、SNSが情報の入手先として着実に浸透すると同時に、情報収集だけでなくコミュニケーションの場としてパイを奪っている実態も指摘される。ポストコロナの時代に、各メディアはどのような戦略で顧客の時間を取りに行くのか。メディアのこれからの可能性を議論する。
ここ10年のAIの進化はすさまじく、我々の日常生活やビジネスの中にも、AIが浸透してきている。責任ある運用によりAIの民主化を図り、日本の抱えるさまざまな社会課題解決につなげていくことが期待されている。この進化の先に私たちはどのような社会を目指していくべきなのか。AIとデータが生み出す社会の現在地と未来への展望を議論する。
外食産業や農業など、労働集約的な「食」にかかわる産業が抱えてきた課題は2年にわたるコロナ禍によって顕在化し、甚大な影響を受けた。一方、コロナ前から続く日本の食に対する世界からの評価の高まりは、決して消え去ってはいない。今後、インバウンドの復活やグローバルサプライチェーンの正常化を見据えれば、日本の食が世界に広がるチャンスは大きい。ポストコロナを見据え、日本の食の課題と可能性を議論する。
コロナ禍で子どもたちの学習環境も大きく変化した。水際対策で日本に入れなくなった留学生たちの学びの現場はどうなっているのか?教育界におけるEBPM(科学的根拠に基づく政策決定)導入の最新動向は?少人数教育の実態や、デジタルの導入の効果はいかなるものか?効果的でより良い教育環境を構築し、新たな時代の人材を育成するためには何が必要か。その課題と方法論を議論する。
テスラのイーロン・マスク氏は温暖化などの「地球課題の解決」を同社のミッションの中心に据え、経営判断を下す際には必ず「この決定は地球課題の解決に資するか」を突き詰めて判断するという。実際、ESGの考え方が急速に拡がり、投資家も消費者も企業の製品ではなく目的から判断して投資や消費を選ぶようになってきた。ポストコロナ時代を見据え、新たな時代に求められる経営のあり方を議論する。
企業経営におけるESGの重要性の拡大やパーパス経営の浸透などによって、Non-profitとFor-profitとの境界線が崩れはじめている。実際、最近では、起業家がお金だけではなく口も手も出して、社会貢献活動を行う例も増えてきている。コロナ禍で様々な社会課題が顕在化する中、政治、経営者、起業家、社会起業家はそれぞれの立場で何が出来るのか。日本を良くするために私たちが出来ることとは。
マンガ・アニメ、ゲーム、食、音楽、アート・・・。多様な現代文化を有する日本だが、世界への発信には課題も多い。またDXと脱炭素化をめぐる世界的競争で旧来型産業が苦戦する中、日本はいよいよ文化領域を成長産業として育てていくことが急務だ。Web3.0・NFTやメタバースという新たな環境変化もある中で、日本はいかに文化発信力と産業競争力を高めていくべきか。
1868年の明治維新から1945年の終戦まで77年。今年2022年はその終戦から数えて同じ77年となる。この日本政治の一つの節目の年に、憲法改正の論議は進むのか。昨年10月の衆院選で改憲に前向きな維新と国民民主が議席を増やし、改憲に向けた条件は整いつつある。国会でも憲法審査会の自由討議が開催され、与党自民党は国民的気運を高める対話集会などを全国で展開する。まさに日本社会のグランドデザインを定める日本国憲法を新時代に適合させるため、改憲に向けた道筋はどのように描かれるのか。
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す持続可能な開発目標SDGs。その達成に向けて国や地方自治体に求められる役割、政府が企業に求める役割、そして企業が国に求める役割とはいかなるものか。グローバルな視点からみえる日本の課題も含め、SDGs達成に向けた展望を議論する。
地球は今まさに変化の時代を迎えている。ブロックチェーン。メタバース。次々に進化する新たなテクノロジー。Web3.0はどのような変化をもらたすのか。数年後には次なるGAFAMが生まれてくるのか。起業家は、不確実性を無数のフロンティアの誕生と捉えて、新たなチャンスをつかむ。今回もトップランナーたちに大いに放談してもらおう。
大学入学共通テスト試験会場の東京大前で受験生ら3人が刺された事件。孤独や自暴自棄からの無差別襲撃で周囲を巻き込む「拡大自殺」。そうした拡大自殺やSNSによる誹謗中傷に耐えかねての自殺が頻発する日本社会の今が示すものとは何か。社会の安全を守り、孤立してしまう人々に手を差し伸べるにはどうしたらよいのか。コロナ禍を経てより深刻化した社会問題を真摯に考える。
コロナによるパンデミックは、人類の英知と努力によって、コントロールできる明るい道筋が見えつつある。パンデミックをチャンスに変えて成長を続ける政治、経済、社会、そして人々。この危機を乗り越えた時、日本と世界はさらに強く、素晴らしい社会を形成しているに違いない。リーダーは困難な時代にこそ自分は何者なのかを考え、自身の使命を明確にし、高い精神性と勇気を持って、仲間と社会をリードしていくことが必要となる。ポストコロナを見据えた世界に向けて、「自覚して行動・提案するG1のリーダーシップ」をG1らしく前向きに全体で議論する。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2022年03月18日(金)〜2022年03月21日(月・祝) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
新型コロナによるパンデミックが世界を覆う中、超大国アメリカのリーダーが変わり、世界のパワーバランスの再構築が進む中迎えた2021年。日本でも新たに発足した菅政権が、コロナ禍をむしろ好機と捉え、今だからこそ出来る規制改革やデジタル改革を進めようとする。コロナを機に非合理的な規制を取り払い、社会のDXを加速し、日本が飛躍するために取るべき戦略とは。
衆議院議員 規制改革担当大臣
スマートニュース株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO
東京大学 大学院経済学研究科・経済学部教授
慶應義塾大学 名誉教授
世界を覆う新型コロナによるパンデミック。世界各国と比べて格段に少ない感染者数に抑えている日本でも、昨年4月、今年1月と緊急事態宣言が発令され、経済活動が大きく制約された。一方、ワクチンの接種もスタートし、通常の社会の復活に向けて明るい兆しも見え始めている。パンデミックを乗り越え、感染拡大防止と経済再生の両輪を回す日本独自の戦略とはいかなるものか。現状の課題と将来展望を議論する。
参議院議員 参議院自由民主党幹事長
株式会社三菱総合研究所 シンクタンク部門副部門長(兼)政策・経済研究センター長 チーフエコノミスト
衆議院議員 経済再生担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣
慶應義塾大学 教授
グロービス経営大学院 学長/グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
菅政権の最大の看板政策のひとつといえるデジタル化。ハンコ廃止などのスモールサクセスからスタートし、デジタル庁によって日本社会のDXを一気に進める算段だ。コロナによる社会の変化をチャンスに変えてこれまで当たり前だった規制やルールを一掃し、日本社会のDXは進展するのか。現状の課題を整理し、DXの方法論を議論する。
富士通株式会社 代表取締役社長 兼 CDXO (Chief Digital Transformation Officer)
ビジョナル株式会社 代表取締役社長
衆議院議員
日本アイ・ビー・エム 代表取締役社長執行役員
衆議院議員
新型コロナによるパンデミックは、世界経済の前提を覆したと指摘される。移動の制約は膨大な需要を消失させ、世界中で格差の問題が深刻化、自国優先主義による世界のさらなる分断も懸念されてきている。これまで当たり前とされてきた、株主利益の最大化やグローバル化を前提とした資本主義は限界を迎え、今後どういった変化を迫られるのか。私たちが持続可能な社会を生きるために必要な資本主義の未来を語る。
衆議院議員
慶應義塾大学 名誉教授
株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長
イェール大学 助教授/半熟仮想株式会社 代表取締役
WisdomTree Asset Management, Inc. Senior Advisor
コロナショックからの経済再生において世界でもっとも注目されるグリーンテクノロジー。菅政権でもデジタル化とならんで最も大きな政策の柱とされる。グリーンテクノロジーは社会をどう変え、今後日本のエネルギー戦略はどういった方向性への転換が必要となるのか。菅政権が2050年ゼロエミッションを掲げる中、達成に向けて必要な技術と戦略、そして私たちの行動とは。
長野県知事
株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO
参議院議員 参議院外交防衛委員会 筆頭理事
国際環境経済研究所 理事/U3innovations合同会社 代表取締役
新型コロナによるパンデミックで社会の分断と断絶がさらに深刻化しつつある今、日本社会におけるインクルージョンの重要性は益々高まってきている。社会から取り残される人を生み出さずに、多様性を包含し、しょうがいを持った人が活躍できる新たな時代の共生社会を実現するためにリーダーが取るべき行動とはなにか。
オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長
社会福祉法人ラーフ 理事長/全国脊髄損傷者連合会香川県支部 支部長
株式会社モルテン 代表取締役社長 最高経営責任者
コロナショックによって最も大きな影響を受けたスポーツビジネスだが、各スポーツの国際大会もコロナ時代における開催方法を発明していき、日本のプロスポーツビジネスも知恵とテクノロジーを最大限に駆使してコロナ時代のプロスポーツ運営の道を歩みだしている。コロナ時代、スポーツビジネスにはいかなる変化が求められるのか。現状の課題とポストコロナへの展望を議論する。
株式会社メルカリ 取締役会長
株式会社ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO
株式会社VICTAS 代表取締役社長
一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事
長期政権の集大成として、これまで先送りにしてきた年金や医療などの制度改革に取り組むとした「全世代型社会保障」を打ち出した安倍政権が退陣し、変わった菅政権は目の前の新型コロナへの対応に取り組まなければならないのが今の日本の現状だ。コロナ対応への莫大な財政出動もあり、日本の社会保障制度を取り巻く環境はさらに厳しくなっている。日本最大の課題ともいえる社会保障制度の改革は今後どうあるべきか、正面から議論する。
法政大学経済学部 教授
参議院議員 経済産業大臣政務官/内閣府大臣政務官/復興大臣政務官
衆議院議員
東海大学 健康学部健康マネジメント学科 健康学部長/教授
グロービス経営大学院 学長/グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
新型コロナの感染拡大は、地域における医療提供体制、特に病院経営の極めて厳しい現状を国民に知らしめた。パンデミックを乗り越え、医療提供体制を安定的に維持するための方法論とはなにか。コロナ対応から見えた医療現場の厳しい実情と課題を把握し、コロナ対応にとどまらず、これからの日本の医療体制、病院経営、医療保険制度を含めた「医療の在り方」を根本的に議論する。
第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長
三重県知事
国際医療福祉大学・高邦会グループ 専務理事
参議院議員/慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授・医学部外科教授(兼担)/弁護士
株式会社麻生 代表取締役社長
新型コロナが社会を変えていく中で、益々その影響力を高める巨大プラットフォーマー。全ての産業のデジタル化が急速に進む中で、経済のみならず、社会や国家にまで及ぶ揺るぎない支配力を所持するに至る。ゲームチェンジのチャンスはどこに潜んでおり、日本企業の可能性はいかなるものか?完全オフレコでGAFAM・BATの本当の脅威を議論する。
スマートニュース株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO
株式会社サイバーエージェント 代表執行役員 社長
株式会社メルカリ 代表取締役CEO
新型コロナによる社会の分断・格差の拡大によって、社会的に弱い立場の人々が置かれている状況はさらに厳しさを増している。少子高齢化が急速に進展し、生産年齢人口が減少する日本において、深刻な人手不足を解消する観点からも、彼らの自立支援を社会として真剣に考える意義は大きい。この不都合な社会課題に対して私たちが出来ることとはなにか。課題解決の方策を探る。
認定NPO法人Homedoor 理事長
認定特定非営利活動法人育て上げネット 理事長
日南市長
衆議院議員 外務大臣政務官
認定NPO法人カタリバ 代表理事
ロックダウンや外出制限で世界中で甚大な影響を受けた外食産業だが、コロナショックを機に、発酵食品文化や食材への敬意など日本の食文化が改めて評価され、今後日本食はさらに世界に広がるだろうといった指摘もある。ポストコロナを見据えた日本の食文化のグローバルな可能性を議論する。
辻調理師専門学校 校長
株式会社京都吉兆 代表取締役社長 総料理長
HAJIME オーナーシェフ/株式会社HAJIME&ARTISTES 代表取締役
農林水産省 国際政策課長
感染拡大防止のための一斉休校など、新型コロナで大きな影響を受けた学校教育現場。人々の行動が制限される中、遠隔教育を基本として学力の向上を可能とする教育方法と学校運営を実現するのは時代の要請だ。コロナを機に、DX、AIによる新時代の教育システム全体の変革を進めるための課題と方法論を議論する。
岡山県知事
慶應義塾 常任理事/慶應義塾大学総合政策学部 教授
衆議院議員
ライフイズテック株式会社 代表取締役CEO
品川女子学院 理事長
新型コロナによってインバウンドが「消滅」した今、観光産業はどうやって生存のための経営戦略を立てているのか。一方、ワクチン接種が世界で進み、ポストコロナに向けた明るい兆しも見えつつある。観光産業は現在の苦境をいかにして乗り越え、ポストコロナの世界にどういった光を見出しているのか。
参議院議員 農林水産委員長
別府市長
アソビュー株式会社 代表取締役CEO
沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役
コロナ時代、キャッシュレスの次の世界はどうなるのか?キャッシュレスによって、ユーザーの属性や動き、購買内容などをデータでとらえることが可能となり、実ビジネスへの展開の可能性が大幅に広がっている。バリューチェーンや販売活動も変化し、AIの具体的な活用事例も出つつある。あらゆる産業のDXの根幹となるキャッシュレスの次の世界を展望する。
Zホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員/ヤフー株式会社 取締役 専務執行役員COO
衆議院議員 衆議院財務金融委員長
株式会社カインズ 代表取締役社長
株式会社マネーフォワード 代表取締役社長CEO
新型コロナの影響によって、子どもの貧困が深刻化している。日本では7人に1人、およそ270万人の子どもが貧困状態にあり、子どもの成長や教育に大きな負の影響を与えているという。先進国の中では米国、イタリアに次いで高い割合だ。そこにコロナ禍の打撃が加わった。子どもたちが、生まれた環境にかかわらず、未来への希望を持ち、自立する力を伸ばすことのできる機会と環境を整えるため、私たちに出来ることとは。
NPO法人新公益連盟 代表理事
慶應義塾大学総合政策学部 教授
参議院議員
認定NPO法人フローレンス 代表理事
世界中でワクチン接種が進み、新型コロナの収束に向けて明るい兆しも感じられるが、日本では7割程度の国民がオリパラ東京大会を延期または中止すべきと考えるとする世論調査も出ている。橋本聖子新組織員会会長のリーダーシップのもと、オリパラ東京大会を実現し、成功させるために何が必要であり、何がベストな開催方式か。そして国民のムードを前向きに変えるために今やれることは何か。限られた時間の中で私たちに出来る行動を議論する。
参議院議員 国土交通大臣政務官
国際フェンシング連盟 副会長/公益社団法人 日本フェンシング協会 会長
株式会社ワントゥーテン 代表取締役社長
オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長
G1メンバーの行動が国を動かし、制度を変え、関係者を動かし始めている。70年ぶりの漁業法改正に端を発した日本の水産改革は現在進行形で進められている途上だ。さんまの漁獲量の激減など豊かだった海洋資源の急減に直面する日本。水産物のトレーサビリティの導入などの改革を実現し、水産業を成長産業に変えることはできるのか。日本と世界の水産資源、海洋環境改革の課題と私たちが取るべき行動について議論する。
株式会社臼福本店 代表取締役社長
東京大学・慶應義塾大学 教授
株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング COO
一般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局 理事長
東京一極集中に加えてインターネットの普及とメディアの多様化も相まって厳しい経営環境を強いられているローカルメディア。しかし、コロナ禍による生活スタイルや社会構造の変化は、地域密着のローカルメディアにとってチャンスとなる可能性がある。これからの時代に、地方のメディアはいかなる情報を発信し、進化していくのか。ローカルメディアのこれからの可能性を議論する。
株式会社茨城放送 代表取締役社長
株式会社東日本放送 代表取締役社長
株式会社京都放送 キャスター
福岡市長
医療現場や医療研究の最先端で5Gやロボット、VRなど最新のテクノロジーを取り入れる動きがさらに加速している。医療はどう進化し、私たちの生活にいかなる変化をもたらすのか。最先端医療の日本の現在地と世界の潮流を展望する。
大阪大学 心臓血管外科 教授
株式会社ビジョンケア 代表取締役社長
UCLA医学部 助教授
Hirate & associates株式会社 代表取締役社長
外国人労働者の受け入れや移民の拡大は、ダイバーシティ・インクルージョンの観点に加え、日本の経済成長の面においても極めて重要な意味を持つ。現在、コロナショックによって外国人労働者を取り巻く環境は激変し、厳しい状況に置かれている外交人労働者も少なくない。ポストコロナを見据え、日本はどういったビジョンに基づいてどういった制度のもとで外国人人材の活用を進めて行くべきか。その課題と展望を議論する。
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役常務執行役員
浜松市長
EDAS 理事長
シンクタンク・ソフィアバンク 代表
5Gによる高速通信・常時接続の高度化によってゲーム・オンラインエンタメビジネスの急速な拡大が見込まれている。そこにコロナ禍による巣ごもり需要がやってきた。しかし、実は日本のゲーム・エンタメ産業は危機的状況にあるともいわれる。ゲーム・オンラインエンタメビジネスを牽引するトップランナーたちはこのチャンスをどう捉え、飛躍への道筋を如何に描くのか。
株式会社ミラティブ 代表取締役
株式会社gumi 取締役会長
グリー株式会社 代表取締役会長兼社長
株式会社ドリコム 代表取締役社長
東京オリンピック・パラリンピック、大阪・関西万博など世界から日本への注目、関心を高めていく道筋は、新型コロナによるパンデミックで一変した。人々の移動が制限され、世界各国で自国中心主義、内向き志向が広がる今だからこそ、グローバルへの発信力が求められる。米中のパワーバランスも変化していく新たな時代、日本の外交力にも直結する「世界への発信力」を高めるため、リーダーができること、そしてやるべきこととは。
株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役会長 兼 社長
コロンビア大学 Adjunct Professor/三菱UFJファイナンシャルグループ 取締役
Mobius Productions 俳優・プロデューサー
リンクタイズ株式会社 代表取締役CEO(Forbes JAPAN ファウンダー)
教科書での定義では「ビジネスは数字と論理」「クリエイティビティは感性」である。しかしクリエイティビティとビジネスは本来一体のものであり、デザイン経営を取り入れる企業は急速に増えてきている。両者の間に横たわる垣根を飛び越えて、経営者はどう価値を作っていくのか?
株式会社 ワークマン 代表取締役社長
株式会社Takram 代表取締役/ロイヤル・カレッジ・オブ・アート 名誉フェロー
株式会社アイスタイル 代表取締役社長 兼 CEO
株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役
折しも第12回G1サミットの第1日目、2021年3月20日に、中村友哉氏が率いるアクセルスペースは、超小型衛星「GRUS」4機を同時に打ち上げる。日本で量産された同型衛星が同時に打ち上げられるのは、国内初の事例になるという。はるか昔、夢やアニメの世界だった宇宙は、20世紀後半、国家の威信をかけたプロジェクトの領域へと移行し、今やベンチャー企業の主戦場へとその姿を変えつつある。マネタイズを実現する宇宙ベンチャーも現れ、宇宙が現実のビジネスとなるこれからの時代に、起業家・政府が取るべき戦略とは。
株式会社ALE 代表取締役社長
株式会社アクセルスペース 代表取締役CEO
株式会社ispace Founder & CEO
衆議院議員
米国バイデン大統領が温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」へ復帰し、世界各国が脱炭素に向けて動き出している。2050年ゼロエミッションを掲げる菅政権のもと、サステイナブルな社会の実現に向けて我が国は今後いかなる行動を進める必要があるのか。脱炭素・サーキュラーエコノミーの実現に向けた戦略と方法論を議論する。
衆議院議員 環境大臣/内閣府特命担当大臣(原子力防災担当)
国際環境経済研究所 理事/U3innovations合同会社 代表取締役
国連事務総長 特使
株式会社日本総合研究所 理事長
SNSであらゆる角度から情報を入手し、発信しあえてしまう現代、私たち人間は本当に自分自身の自由意志に基づいて意思決定を行うことができているのか?ニュースソースがSNS主体の若い世代において、その傾向はいかなるものか。SNS主体の時代における、より良い意思決定システムをいかに構築するか、自由意志から人間の本質を考える。
一般社団法人リディラバ 代表理事
東京藝術大学デザイン科 准教授
慶應義塾大学 特任准教授
一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事
コロナショックによって人々のライフスタイルや住む街への意識は一変した。東京一極集中から、地方都市へ移住する人も増え、働き方も多様化した。ソーシャルディスタンスと移動の極小化が求められ、テクノロジーの発達によって多様な働き方、生き方が可能となるコロナ時代に人々は都市に何をもとめ、都市はいかなる機能を備えるべきか。コロナ時代の都市とインフラの未来を考える。
つくば市長
Toshiko Mori Architect PLLC建築事務所 創立者CEO/ハーバード大学院 教授
森ビル株式会社 取締役副社長執行役員
株式会社サキコーポレーション ファウンダー
今、Well-beingという概念を経営戦略に取り入れる企業が増えている。地球環境や人々の幸せや精神的な豊かさ、経営にまつわるすべてのステークホルダーと調和しようというWell-beingとは、企業経営に如何なる価値をもたらすのか。その実態を解き明かしていく。
株式会社アカツキ 共同創業者
慈眼寺 住職
衆議院議員 総務大臣政務官
株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO/株式会社日立製作所 フェロー
株式会社プロノバ 代表取締役社長
2000年以降急速に拡大してきた日本のスタートアップエコシステム。ユニコーン企業も生まれたが、デカコーン、ヘクトコーンをも生み出す米国など海外勢との格差は未だ大きい。シリコンバレー一強時代からの過渡期とされる今、日本のスタートアップエコシステムにとって大きなチャンスとなる。日本からグローバルNo1企業を輩出し続ける為に何が必要か。
東京大学 大学院工学系研究科 教授 産学協創推進本部 副本部長(兼務)
合同会社DMM.com 会長
グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
東京大学大学院工学系研究科 教授
ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO
コロナショックはソーシャルビジネスにいかなる影響を与えているのか。ITを中心としたスタートアップの活動領域が社会において拡がる中、かつてNPO、非営利団体と言われた業界と営利企業との垣根はどんどん低くなっている。コロナや災害時において、個人や企業には何ができるのか、ソーシャルセクターの現場はどういうタイミングで、どのような資金を求めており、リターンはいかなるものか。コロナ禍におけるソーシャルビジネスの最前線を解き明かす。
一般財団法人ジャパンギビング 代表理事/NPO法人ドットジェイピー 理事長
READYFOR株式会社 代表取締役CEO
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO
NPO法人 ETIC. 代表理事
今後、米バイデン政権はいかなる安全保障戦略を展開し、米中関係はどうアジアに影響を与えるのか。コロナショックも相まって輸出入規制・投資規制・ハイテク技術移転など外交手段としての経済政策の重要性が高まる中、一帯一路を含め、各国の広域経済秩序構想の影響はどう出てくるのか。今回のG1サミットで唯一の外交を考えるセッションで、安全保障・経済外交にわたって日本外交のアジェンダを展望する。
笹川平和財団 上席研究員
外務省 経済局長
慶應義塾大学総合政策学部 教授
ミルケンインスティテュート アジアフェロー/国立シンガポール大学リークワンユー公共政策大学院 兼任教授
2021年以降の世界では、企業経営におけるESGの重要性がさらに高まっていきそうだ。米バイデン新大統領も日本の菅政権も気候変動への課題を最重視しており、環境への投資は世界の潮流だ。パンデミックによってソーシャルの視点もさらに重視され、企業ガバナンス強化の重要性も論を待たない。ESGはいかなる企業においても、経営上の最重要課題の一つとなったといえよう。世界におけるESGの最新の潮流を議論する。
株式会社丸井グループ 代表取締役社長
国連事務総長 特使
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員
株式会社ユーグレナ 代表取締役社長
世界各国でAIや自動運転の研究開発・社会実装への動きが加速している。日本のAI×ロボットテクノロジーが持つ可能性はいかなるもので、今どこまで進んでいるのか。私たちの社会をいつ、どこまで変えていくのか。ロボット実装に向けた国際競争において日本が世界をリードする可能性はどこまであるのか。AI・ロボットの最前線を議論する。
株式会社PKSHA Technology 代表取締役/工学博士
川田工業株式会社 代表取締役社長
株式会社Preferred Networks 代表取締役 最高経営責任者
村田機械株式会社 代表取締役社長
コロナショックは東京以外の地方都市にとって新たなチャンスとなっていくのか。働き方の多様化により地方都市へ移住する人も増え、人々のライフスタイルも多様化した。コロナ禍をチャンスに変え、メガ都市への一極集中トレンドを変えることは、可能なのか。各都市がそれぞれに魅力的な発展を遂げ、一極集中型の未来に対するオルタナティブを創る戦略を議論する。
慶應義塾大学環境情報学部 教授/ヤフー株式会社 CSO (チーフストラテジーオフィサー)
株式会社ジンズホールディングス 代表取締役CEO
奈良市長
NPO法人地域から国を変える会 理事長/青山社中株式会社 筆頭代表(CEO)
株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 代表取締役社長
コロナに伴う経済活動の制限により、リアルのエンタメ産業は大きな打撃を受けた。一方でオンラインに新たな活路を開き、コロナを機に新機軸を展開する動きも出始めた。コロナ・5G時代、コンテンツ・エンタメ産業の未来はどう進化していくのか。コロナを機にテクノロジーと融合し、新たな時代を切り拓く戦略とは。
UUUM株式会社 代表取締役社長CEO
セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役社長 グループCOO/株式会社セガグループ 代表取締役社長CEO/サミー株式会社 代表取締役社長CEO
アソビシステム株式会社 代表取締役
A.T.カーニー株式会社 日本法人会長/CIC Japan 会長
あの3月11日から10年。この10年で、東北復興はどう進んできたのか。この先、日本の未来のために必要なことは何か。復興への取り組みを地道に続けてきた人々が今抱える課題、そしてこれからの日本に望むものとは。力強く復興する東北の現状と課題、そして見据える日本の未来を議論する。
福島県知事
仙台秋保温泉 佐勘 代表取締役
女川町長
衆議院議員
一般社団法人RCF 代表理事
新型コロナによって昨年初めて「中止」を余儀なくされたG1サミットだが、コロナ禍における安全なカンファレンス開催の方策を1年を通じて進化させ、大震災から10年の節目の年に、宮城県秋保の地で共に学び、G1最大の強みといえる仲間のネットワークをさらに強固なものとする時間を共有した。コロナが世界を暗く覆う中、私たちG1メンバーは、日本と世界の変革の先頭を走り続けるために今いかなる行動をとるべきか。それぞれの立場での次なる「行動」の道しるべを全体で議論する。
株式会社サキコーポレーション ファウンダー
株式会社日本総合研究所 理事長
参議院議員
グロービス経営大学院 学長/グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2021年03月20日(土)〜2021年03月21日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
約6年間のアベノミクスによって、国内総生産(GDP)は上昇を続け、企業収益は過去最高水準にある。官邸の強いリーダーシップの元に経済政策の舵取りを成功させ、様々な規制改革、働き方改革、農協改革、さらには農林水産業改革まで着手してきた安倍政権。この政権にとって、社会保障改革は残された最後の聖域の一つといえるだろう。憲政史上最長政権はこの後、いかなるレガシーを残そうとするのか。経済と社会保障について議論する。
地球を俯瞰する外交を続けてきた安倍政権だが、英国のEU離脱やトランプ政権の自国第一主義、中国・ロシアの大国化路線、東南アジアや中東における紛争など、世界秩序は新たな時代に向けて急速かつ大きな変化を続けている。国内に目を向けると、世界の中で存在する日本として、この国の形を決めるのが憲法だ。安倍総理が悲願としてきた日本国憲法の改正は今年いかなる路を辿るのか。官邸のキーマン西村康稔内閣官房副長官と、新進気鋭の論客三浦瑠麗氏を交え、神保謙慶應大学教授が大局的な視点から今後の道を照らす。
安倍政権に残された最後の、そして最大の聖域といえる憲法改正。与党は2019年の通常国会に憲法9条への自衛隊明記など4項目の党改憲案について、2019年の通常国会で各党に提示し、討議を進めていきたいとの考えを示している。憲法改正に意欲を示す総理大臣の存在、改正発議に必要な国会の議席の3分の2を与党が確保している状況、そして野党の側にも改憲派がいることの3点がそろっている今の状況はす数十年に一度の「惑星直列」といえるという。このチャンスをいかせるか否かは、私たちの「行動」にかかっている。
企業の長期的な成長の観点から持続可能な社会の構築に貢献するE(Environmental 環境)、S(Social 社会)、G(Governance ガバナンス)は、いまや強力なグローバルトレンドとなった。世界各国で広がる環境破壊や、労働者を酷使する人権問題。ESGに力を入れる企業への投資が急増し世界で2500兆円を超える一方で、「十分に配慮していない」と見なされた企業からは資金が引き揚げられる。このトレンドから日本企業だけが逃れられるわけはない。ますます急速に拡大する「ESG投資」「ESG経営」の潮流を議論する。
内燃機関というテクノロジーを社会に爆発的に普及させたアプリケーションは「車」であった。同様にインターネットのそれは「検索」と「eコマース」であった。ではAIでは何がトリガーとなるのか?それは「ロボット」であるという。「ロボット」は、従来の最大セグメントである工業用ロボットに加えて、物流、農業、医療・介護、建設・設備メンテナンス、警備、清掃などに様々な用途が広がる。家庭用ロボットも既に普及しつつある。幸い、ロボット分野は日本の得意分野だ。特に交通や医療などの高い信頼性が求められる領域でも日本の強みは発揮されるだろう。日本が世界に先駆けて「AI×ロボティクス」のアプリケーションを開発し、世界で勝つための戦略とは何か。トップランナーたちの議論からAIの未来を読み解く。
「全世代型社会保障」を打ち出した第4次安倍政権。本格的な社会保障改革となれば国民に痛みを負担させることとなり、政権最大のチャレンジとなるだろう。人生100年時代を控え、負担が現役に偏りがちとされる日本の社会保障制度をどう変えていく必要があるのか。65歳定年制の廃止は?増大する一方の社会保障費の抑制策は?年金受給年齢の引き上げは?日本が直面する課題の解決策を議論する。
昨年4月から9月にかけて3度もの南北首脳会談が行われ、非武装地帯(DMZ)付近の武装解除、2019年中の金委員長のソウル訪問など南北間の歴史的な展開が生じつつある朝鮮半島。一方で、米朝両国の間の非核化交渉については、昨年6月の電撃的な米朝首脳会談以来、これといった進展が見られておらず、北朝鮮による核分裂物質の生産は続いている。日本の安全保障環境を考えれば、朝鮮半島での動きは最大の懸案だが、東シナ海や南シナ海を含むインド太平洋地域を大きく俯瞰してみる必要がある。予測できない朝鮮半島の情勢に対応し、自由で開かれたインド太平洋地域で日本の安全保障を確立するための戦略を探る。
ESG投資のため企業の環境情報開示を進める、G20の要請を受け金融安定理事会(FSB)が設置した「気候関連財務開示タスクフォース(TCFD)」の取組、英国本部の国際NGO「CDP」や企業が使用する電力を100%自然エネルギーに転換することを支援する国際的なイニシアティブ「RE100」など、昨今、企業の気候変動対策についての情報開示・評価の国際的なイニシアティブの影響力は益々大きくなっており、日本と日本企業もこうした動きに対応することが求められている。エネルギーはライフラインであり、特に人口減少や過疎化に直面する日本は世界に先駆けて社会インフラとしてのエネルギーを気候変動問題と整合的に解決していく政策をとっていくことが必要だ。エネルギーインフラの維持をエネルギー事業だけで解決できる時代は終焉した。エネルギーとモビリティ、エネルギーと農業、エネルギーと金融といったクロスセクターの取り組みによる社会変革はどうすれば可能なのか、徹底討論する。
今やAIは世界各国の幅広い産業分野に取り込まれつつあり、特に米国と中国における進展は目覚ましく、官民一体となった社会実装が図られている。それは AIの社会実装を他国に先駆けて実現することが、国家や産業の行く末を決める鍵とみられているからだ。翻って日本では、政府はSociety5.0を掲げるものの、AIの利活用は先進的な一部の企業や先導的な産業分野にとどまり、社会一般への実用化には至っていない。しかし、AIの社会実装こそが日本が世界にリードし得るテーマであり、日本企業が世界で勝つための突破口となるのは間違いない。AIの社会実装を世界に先駆けて進めるために必要なことは何か。
少子化対策は経済成長戦略であり、少子化を放置したままでは日本は衰退してしまうという問題意識のもと第10回G1サミットでの議論をもとにG1少子化イニシアティブがスタートした。海外の事例を研究すると、結婚へのハードルを下げたフランスのPACS制度や子供の数に応じた税の優遇制度N分のN乗方式など、出生率の上昇につながる策は多い。政治、経済、社会が一体として行動し、少子化に歯止めをかけるための政策、施策を進めるためにG1メンバーが出来ることとは何か。イニシアティブでの議論を踏まえ、具体的な行動につなげる。
休眠預金の新制度が今年いよいよ動き出す。10年出し入れのない金融機関「休眠預金」のお金をNPOや市民団体の公益活動に充てる制度だ。休眠預金は毎年700億円規模で発生しており、第一弾の資金は秋にも交付される見通しだ。これをNPOの活動に充てられる新制度が回り始めれば、日本のNPOの活動の幅も拡がるだろう。E(Environmental 環境)、S(Social 社会)、G(Governance ガバナンス)が強力なグローバルトレンドとなる中、企業経営にとってもソーシャルな活動への関与の仕方は優先度の高い関心事となっている。ソーシャルビジネスを成長させるお金の使い方はいかなるものか、企業経営者はソーシャルビジネスとどう向き合うべきか、徹底討論する。
麻布、開成、灘などの男子校と並んで、女子校が改めて評価され始めている。共学別学といい、部活や生徒会は一緒にやるが、授業は別に行う学校も出てきた。国際的にも、男子校と女子校は厳然としてあり、男女の「性質」の違いを意識して中等教育を行うsingle-sex schoolの重要性は近年見直される傾向にある。女子教育を変え、女性リーダーを増やすためにいかなる戦略が必要か。教育改革実践家藤原和博氏が、教育改革の最前線に立つパネリストたちと徹底討論する。
少子高齢化が著しく進展し、生産年齢人口が減少する日本において、深刻な人手不足を解消するため、外国人労働者をはじめとした様々な労働力を幅広く確保することが喫緊の課題となっている。外国人労働者の受け入れを含めた雇用のダイバーシティの議論の大前提は構造改革であり、民間における生産性向上が何よりも優先されるべきであり、重要なのはダイバーシティの拡大によりバリューチェーンの構造改革が促進され、生産性を高め、賃金の底上げ、経済社会の活性へとつながることだろう。差別の助長や移民反対等の安易な反対論を超えた、日本社会のあり方を考える。
インターネットやAIがあらゆるビジネスを根底から変えていくといった議論が陳腐に聞こえるほど、テクノロジーによる変化はすさまじい。もはや3年後の世界がどうなっているかを正確に予測することは不可能といってよいが、新たなチャンスをつかむためには、イノベーションを取り巻く環境でどのような地殻変動が起こっているかを経営者が感覚として把握しておくことが重要だ。今回もトップランナーたちに大いに放談してもらおう。
安倍政権が掲げる「全世代型社会保障改革」の医療改革では、予防医療と遠隔医療が改革の柱となりそうだ。予防医療では、人生100年時代に向けて、糖尿病、高齢者虚弱、認知症の予防に取り組み、自治体などの保険者が予防施策を進めるインセンティブ措置の強化を進めるとともに、遠隔医療(次世代ヘルスケア)では、オンライン医療の推進を図る方針だ。2018年度診療報酬改定では初めてオンライン診療料が新設されており、その対象の拡大やオンライン服薬指導の提供体制の整備や法制的な対応も重要な課題となる。最先端のテクノロジーを活用し、持続可能な医療制度をつくるにはいかなる改革が必要か。政治、医療経営、テクノロジー等の観点から議論する。
昨年初めて3000万人を突破した訪日外国人たちを魅了してやまない日本の食。自然や四季との調和を追求する文化としての日本食は、伝統を受け継ぐと同時に時代の変化に応じて変革・イノベーションを起こし続けてきたからこそ、世界中に評価されるのであろう。「和食・日本人の伝統的な食文化」がユネスコの「無形文化遺産」に登録されて5年が経過し、TOKYO2020も直前に控える今、日本の食文化を世界へ発信し、次世代に引き継ぎいでいくために、私たちは何をすべきか。世界の食に携わるトップランナーたちが徹底的に議論する。
日本の人口は2008 年をピークに減少局面に入り、65 歳以上の高齢者人口は3515万を超え、総人口の27.7%と最高を記録、我が国の高齢化は、世界的に見ても空前の速度と規模で進行している。一方で、各地域の努力にも関わらず、人口移動面における東京一極集中の傾向は継続しており、東京圏への人口流入は止まっていない。地域における人口減少と地域経済縮小を克服するためには自立した地域が独自の発想で官民を上げて地方創生に取り組み、各地域が日本をリードしていくことが必要だ。地方創生の最前線を走るキーパーソンたちが議論する日本の未来。
2018年、訪日外国人が初めて3000万人を突破した。15年前はたった500万人だったことを考えれば、政府や民間のこれまでの取り組みは大いに評価されてよいだろう。政府の掲げる次なる目標は「2020年に4000万人、30年に6000万人」だが、観光大国フランスにも引けを取らない豊富な観光資源を全国に持つ日本のインバウンド政策は、今後は数とともに質を追求する必要がある。米国の大手旅行雑誌「コンデ・ナスト・トラベラー」の「旅行先として魅力的な世界の大都市ランキング」では、昨年、東京が1位、京都が2位となった。世界が認める魅力を持つ日本のインバウンド大国への道とはいかなるものか。最新動向と現状課題を踏まえ、2020年以降の具体的な成長戦略を語る。
PayPay(ペイペイ)、merpay(メルペイ)、LINEPay(ラインペイ)と、現金大国ニッポンにもいよいよキャッシュレスの大波を起こそうとする新たなチャレンジが巻き起こりつつある。彼らの挑戦は、中国、韓国に周回遅れの日本をキャッシュレス先進国に作り変えることができるのか。まさに最前線で日本のキャッシュレスを牽引するトップランナーたちの議論から、近未来の日本の姿を考える。
2016年に予防医療普及協会を設立した堀江貴文氏は、その後、胃がんの主な原因であるピロリ菌の検査・除去啓発のプロジェクトや大腸がん予防のプロジェクトなど様々な啓蒙活動を実施してきた。堀江氏が今最も力をいれているのが、子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染予防だ。著書『健康の結論』でも、予防医療の重要性を訴える堀江氏を迎え、医療現場や政治のキーパーソンを交え、科学的データに基づく予防医療によって高パフォーマンスで人生100年時代を生きる戦略を議論する。
地震、豪雨、台風と、ここ数年は毎年、激甚災害に指定されるほどの災害が立て続けに発生し、その数は過去5年で27件にも及んでいる。日本が地震活動期に突入し、地球温暖化によって豪雨災害の規模が過去と比較にならないほど大きくなる中、誰もがある日突然、地震や水害といった災害に遭い、被災者となることを覚悟しなければならない時代となった。行政、政治、NPO,民間企業それぞれの立場から自然災害に立ち向かうメンバーたちの議論から、平時・有事それぞれに必要な取り組みを考える。
温室効果ガスの削減や渋滞緩和、公共交通機関システムの改善、治安、インフラ設備の老朽化、市民生活の向上など都市が抱える多様な問題を一元的に解決するために、センサー、IoTなどのテクノロジーを駆使して拡張性の高いプラットフォームを構築するスマートシティに注目が集まっている。欧米の各都市でもスマートシティ導入への関心は高まるばかりだ。2000年からスマートシティに取り組んでいるバルセロナでは、道路に車両のスピードセンサーを埋め込み、自動車の速度が一定を超えると次の信号が自動的に赤になるアプリケーションで事故を未然に防ぐなど、先進的な取り組みが進んでいる日本でも2019年から政府は本格的にスマートシティの実現に向けて動き出す。スマートシティによる日本再生の鍵とは何か。専門家たちの議論から読み解く。
インバウンド観光・コト消費の拡大の切り札として注目を集めるナイトタイムエコノミー。ロンドンの夜間経済GDP 3.7兆円、ニューヨーク・ブロードウェイの経済効果1.4兆円を鑑みると、TOKYO2020を控える東京でも数兆円規模のGDPポテンシャルが存在する。大都市はもちろんだが、観光による成長を目指す地方都市にとっても重要なテーマだ。さらに夜間経済の活性化は、ライフスタイルの多様化や文化の成熟という文脈でも大きな意義を持つ。風営法改正とナイトタイムエコノミー創造に取り組んできた官民のキーパーソンが展望と課題を議論する。
ポータルサイトやSNSが登場し、ニュースはマスメディアに限らず誰もが配信・享受できるものへと変わった。情報発信にともなう責任の境界は次第に曖昧になり、その間隙をついてフェイクニュースが広がっていった。テクノロジーの進化と人々の行動様式の変化を考えれば、ネットメディア市場の成長は不可逆的だろう。6兆円といわれる国内メディア市場のうち、ネットメディアは2018年で1.5兆円、22年には2.4兆円に成長すると予想されている。成長するネットメディアの信頼性を担保し、さらなる成長を図るための方法論を議論する。
昨年、人の尊厳として「どう生きるか」と同じように「どう死ぬか」の選択肢を権利として確立するためのG1イニシアティブがスタートし、「死を語り合える雰囲気作り」「各国事例研究」、「医師の負担軽減」等を軸として、尊厳死や安楽死の法制度化の可否やその内容が議論されてきた。実体験や価値観の違いから多様な意見が出るこの深遠なテーマについて、イニシアティブでの議論をもとに慎重かつ大胆な議論を進める。
世界中で急激に盛り上がりを見せているe-Sports。e-Sports元年とも言われた昨年、2月にはJeSU(一般社団法人日本e-Sports連合)が、プロライセンスの発行や公認タイトルの認定、高額賞金付き大会の解禁、そして、これまで分かれていた5つの関連団体の統合・協力を発表した。これによって日本のe-Sportsが前進し、様々なゲームタイトルで、e-Sports大会、リーグ、そしてプロチームが立ち上がり、毎週のように日本全国でe-Sports大会が開かれるようになった。今後日本のe-Sportsシーンはいかなる展開を見せるのか。日本のe-Sportsが世界に打って出るための課題と戦略を徹底議論する。
2018年11月に初めて開催された「G1海洋環境・水産フォーラム」。G1メンバーがイニシアティブとして行動してきた成果が国を動かし、制度を変え、頑なだった関係者を動かし始めている。世界では水産業の成長産業化に多くの国が成功している中、豊かな海洋資源を持つ日本だけが漁獲量の減少の一途をたどっている。世界では常識となりつつある水産物のトレーサビリティもなかなか浸透していない。適切な水産資源管理、海洋環境保全を実現しながら日本の水産業が成長していくために私たちが取りえる行動とは。
グーグル、アマゾン、アップル、フェイスブック、マイクロソフト、アリババ、テンセント。ネット上でデータを囲い込む米中の巨大プラットフォーマー「セブンシスターズ」の優位は絶対的だ。これら世界の巨大資本プラットフォーマーに日本企業が対抗する術はあるのか。それとも異なる視点から別次元の競争をしかけるべきなのか。グローバルな視野で経営戦略を進めるトップランナーたちの議論から日本の戦略を探る。
近年、宇宙関連スタートアップへ急激に資金が集まり始めている。宇宙関連スタートアップへの投資は世界で2500億円まで膨らみ、日本でも大型投資が相次いでいる。衛星データ活用や小型衛星の開発など、ビジネス上の成果が顕在化するのも間近だろう。政府も、宇宙開発スタートアップに1000億円を投じる支援枠を設け、2030年代に国内宇宙産業の市場規模を2兆4000億円と現在から倍増させることを目標としている。本格化する宇宙ビジネスにおいて日本が取るべき戦略とは。
再生医療の分野で世界の最先端を走る日本。再生医療関係法の施行によって、有効性が推定され安全性が確認された場合に、条件及び期限付きで特別に早期に承認される日本独自の制度が整備され、日本は再生医療製品の製品認可を世界最速で取得できる国となった。現在までに、理研等のチームにより世界初の加齢黄斑変性に対するiPS細胞由来の網膜細胞移植の臨床研究が実施され、京都大学ではパーキンソン病に対するiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞移植の治験が開始された。大阪大学は、iPS細胞から作った心筋シートによる心臓病(重症心不全)治療で世界初の再生医療製品化を目指している。海外から日本へ再生医療の研究開発拠点を移す企業も相次ぐ。進展する日本の最先端医療の今後の展望を語る。
TOKYO2020がいよいよ翌年に迫った。大会ボランティアの募集も始まり、競技施設の建設も大詰めを迎え、史上最多の33競技339種目で争われる祭典の代表選考も本格化する。昨年初めて3000万人を超えた訪日外国人も2020年には4000万人を見込む。昨年には卓球Tリーグも開幕するなど、国内スポーツリーグも大いに盛り上がっている。翌年に控えたTOKYO2020に向けた課題と展望とは。
日本の科学技術の低迷が叫ばれている。研究の影響力の指標とされる論文引用数で、東京大学は392位、京大は518位にとどま り、中国勢や欧米に大きく水を開けられている。日本の科学技術関係予算がほぼ横ばいの間に、米国や中国は潤沢な予算をAIや宇宙開発など最先端の研究に投資してきた。このままでは、日本の科学技術は世界から取り残されてしまうだろう。新たな時代の日本の科学技術・イノベーション戦略とは。
次の10年のスタートを切ったG1サミット。世界の変化のスピードはさらに加速していく。日本が世界からマージナライズされるのではなく、変革の先頭を走り続けるために今何をすべきか。そして、私たちG1メンバーが取るべき具体的行動とはいかなるものか。初日のナイトセッションで議論された「100の行動2.0」を各グループより発表してもらい、全体で議論する。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2019年02月09日(土)〜2019年02月11日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
第1回G1サミットのテーマは「2020年の日本と世界」であった。10年目を迎えた今、多くのG1メンバーが日本の中枢を担い、それぞれの分野で世界をリードする姿が現実のものとなった。10周年を迎えさらにパワーアップしたG1は次の10年に向けて今いかなる行動をすべきか。世耕弘成氏、竹中平蔵氏が考えるこの国の未来を小泉進次郎氏が引き出す。
英国のEU離脱やトランプ政権の誕生。中国・ロシアにおける国家資本主義の台頭。そして、中東・アフリカやミヤンマー等に見られる紛争。一方では、躍動感ある日本外交、ESGなどで積極的に世界をリードするGPIF、国際機関の中でリーダーシップを発揮する日本人の存在。100の行動の中で最も力を入れた章が「世界の中の日本」であった。新たな時代への過渡期に位置する今、外交、金融、国際機関から見た日本の課題と可能性を語る。
「亀田興毅に勝ったら1000万円」「藤井聡太四段 炎の七番勝負」「72時間ホンネテレビ」など、次々と話題の番組を仕掛ける「Abema TV」。ネットメディアが既存メディアを凌駕する日は近いのか。サイバーエージェント藤田晋氏が描く次なる一手は何か?既存メディアの対抗策は?動画配信メディアの未来を語る。
ispaceは昨年12月、スタートアップとしては世界過去最高額となる総額101.5億円の資金調達を実施すると発表した。今後、月面資源を軸にした民間の宇宙ビジネスシステムの構築、その先にある人類が宇宙で生活できる持続的な人類社会の創造が現実となってくる。宇宙における新たな国際秩序の構築も急務だ。宇宙ビジネスの最前線をキーパーソンたちが語る。
国土の7割を森林が占める日本は、温帯地域に位置し雨が多く樹種も豊富であり、日本の森林資源は質・量ともに世界トップレベルである。木材は東アジアへの輸出が年々増加しているが、日本林業はGDPの0.1%以下であり、生産額より補助金が多く、衰退産業化して久しい。また、現行林業による大規模な皆伐や過間伐は、豪雨が頻発する現在、土砂災害の被害拡大要因になっているとの批判もある。世界に誇る森林資源を持続的に利用・保全しながら、無垢材等の付加価値材の輸出拡大を通じ、日本林業を補助金依存産業から地域再生を担う一大産業に成長させる戦略を議論する。
変革を実現するためには、確固としたビジョンを打ち立て、発信し、そのビジョンに共鳴する同志を集めることが不可欠となる。そのための武器が「コミュニケーション」だ。奥山清行氏、小泉進次郎氏、松山大耕氏が語る「ビジョンを伝えるコミュニケーションのアートとサイエンス」とは。
2017年、日本を訪れた外国人は11月末時点で2,617万人と2016年1年間の2,404万人を超えた。政府は昨年「観光立国推進基本計画」を改定し、2020年までに、1)国内旅行消費額を21兆円にする、2)訪日外国人旅行者数を4,000万人にする、3)訪日外国人旅行消費額を8兆円にすると目標を底上げした。「世界が訪れたくなる日本」への飛躍を図るために取るべき戦略とは。
欧米で急速に広がるシェアリングエコノミーの威力はすさまじい。ユーザーと提供者を直接つなぐプラットフォームが形成され、物、場所、時間や労働力の使われ方を劇的に変化させ、その市場を急速に拡大させている。一方日本では、2014年に東京でタクシー配車サービスを開始したウーバーは、すでに東京からは撤退。また、昨年6月に民泊を全国で解禁する「民泊新法」が成立したものの、各地域の条例や自主規制でこれを阻む動きも広がる。日本が世界から取り残されないための方策とは。
北朝鮮による弾道ミサイル発射と米国への挑発はエスカレートする一方である。中国の海洋での活動も活発化しており、我が国が位置する東アジア地域は世界で最も安全保障環境の厳しい地域の一つであるといっても過言ではない。米国の孤立主義志向が明確になる中、日米同盟における日本の役割をより強固にし、同盟を進化させる必要性に我々は迫られている。めまぐるしく変化する国際情勢の中で日本がとるべき新たな安全保障政策とは。
「ポストトゥルース」とは、「世論の形成において、感情や個人の信念に訴えかけるものの影響力が、客観的な事実の影響力より大きい状況」だ。米大統領選挙でトランプ氏が当選したことを機にフェイクニュースが世界でも大きな関心を集めるようになり、昨年4月にはニューヨーク市立大学ジャーナリズムスクールが「ニュース・インテグリティ・イニシアティブ」の設立を発表、日本でも6月にメディア事業者やジャーナリスト、研究者らによって「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」が設立された。対策にはジャーナリズム、SNS事業者、政府、企業、個人、それぞれの努力が必要となる。
人生100年時代が到来する一方で、医療制度をめぐる課題は山積し、人口減少、社会保障コスト負担の抑制の議論の中で、病院経営の担い手が減少するであろう将来も充分認識されているとは言い難い。遠隔診療など技術革新は、医療制度改革の突破口となりえるか。医療制度、医療経営を持続するために足りない議論は何か。現場の視点から医療制度、医療経営の未来を語る。
AI関連産業の市場規模は2030年に約87兆円とも試算される。すべてのものがインターネットでつながり、蓄積されるビッグデータが指数関数的に増大する中、AIは社会と産業の構造を根底から変えようとしている。AIの進化がもたらす新たなパラダイムにおいて、企業経営にはいかなる変革が求められるのか。AI経営の最先端をいくキーパーソンたちが語るAI時代の経営戦略。
G1プラットフォームを活用して政界、財界、学会の各分野を巻き込み、海洋環境の問題解決と海洋政策を進めることを目的に2017年11月にG1海洋環境研究会が発足した。主に「公害 Pollution」「気候変動・温暖化 Climate Change」「乱獲 IUU」といった分野について研究を進めることとなる。国連の提唱する持続可能な開発目標・SDGsの14番が「海を守ろう」だ。EEZ世界第6位を誇る日本の海洋戦略とは。東京五輪を目前にやるべき事とは。G1海洋環境研究会のキーマンたちが語る。
河野太郎外相は昨年11月、政府のレセプションの招待者について、「法律婚・事実婚あるいは同性、異性にかかわらず、配偶者またはパートナーとして接遇するよう指示した」と明らかにした。多様性を認め、多様な人材が活躍できる環境を整えることは、少子高齢化の中で人材を確保し、経済の持続的成長を図る上で、政府、社会、企業経営者それぞれが取り組むべき課題だ。社会の景色を変えるべく活動する先駆者たちが、社会と経済、企業の関係をとことん語り尽くす。
五千円札に描かれていた新渡戸稲造は、日本人として初めて国際連盟事務次長となっただけの人物ではない。日本人とは何かを世界に発信し続けた傑人だ。新渡戸稲造が「武士道(Bushido)」をフィラデルフィアで刊行したのは1900年。突如世界に現れた新興国日本に対して世界中が「何者だ?」と感じていた時代に、新渡戸は「日本人とは何か」というプロパガンダを打ち、この「武士道」が一気に世界的ベストセラーとなった。今、世界に分断と保護主義が蔓延している中、経済的にも政治的にも安定している日本の役割は大きい。世界が関心を持つ日本となるために、私たちが取るべき行動とは。
インターネットが産業と社会を変え、既存のビジネスを過去のものにしていくスピードが加速度的に増加していることは論をまたない。世界ではGoogle、Apple、Facebook、AmazonのGAFA勢を筆頭に、個人の情報、行動、ネットワークをクラウド上にビックデータとして押さえ、次の儲ける仕組みをつくるため莫大な投資が進められる。巨大な外資に対抗し、新たな時代の「稼ぐ仕組み」を誰がどうつくるのか。異才たちの世界観と次なる一手とは。
2020年までに大学入試センター試験は終了し、代わりに「大学入学共通テスト」が導入されるが、この入試改革と指導要領改革を「ゆとり教育」の二の舞にしてはならない。AI時代の到来で世の中は激変している。教員の世代交代が進み、基礎学力のみならず「情報編集力」を鍛え、より人間的な仕事のできる人材育成の教育が必須となってくる中で、思考力・判断力・表現力に優れた問題解決型のリーダーは育成できるのか?・・・教育の2020年問題をリーダーたちが徹底討論する。
ふるさと納税で寄付を受ける自治体がNPOや企業と連携して社会課題解決のインパクトを高める仕組みはコレクティブインパクトの新しいカタチといえるだろう。複雑な社会問題に取り組むソーシャルビジネスの世界において、組織や業界の壁を越えたコラボレーションは不可欠となる。ソーシャルセクター、ビジネスセクター、ポリティカルセクター、ガバメントセクターとの相互連携によって規模化を実現し、社会課題解決のインパクトとスピードを高める方策とは。
デジタル市場で急成長を遂げたGAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)のようなプラットフォーマーは、クラウド上に集積されたビッグデータを新たな付加価値の源泉としてその競争優位を固定し、支配的地位を確立しようとしている。今や競争環境が変化していることは自明であり、欧米の当局も競争政策の改革を手さぐりで進めている。日本の競争力を損なわず、むしろ高めるためには何が必要か。キーパーソンたちが議論する。
2022年に期待するテクノロジーについて800人のビジネスパーソンに聞いた日経BP総研の調査では、「再生医療」を筆頭に1位から10位までのうち、4つが人の命に関するテクノロジーとなった。中でもiPS細胞は、生命科学分野において無限の可能性を持つ。iPS細胞を用いた再生医療や創薬の世界で日本が生き抜くための方策とは。
2018年、安倍首相は「時代に対応した国の姿、理想の形をしっかりと考え、議論していくのは歴史的な使命だ」と任期中の憲法改正に並々ならぬ意欲を示した。いよいよ憲政史上初の国民の国民による憲法改正が現実的となってきた。憲法改正を拒絶する「護憲」の発想から脱却し、憲法改正を前向きに捉え、すべての政党やシンクタンクが憲法草案を出し、国民的議論を巻き起こすプロセスに持っていくには。
世界の都市間競争の主役は、知識創造産業がリードするクリエイティブなシティだ。ユニークな文化と先端的な産業を集積した魅力的な都市をつくるために、ポスト2020のTOKYOはどんな発展を志向すべきか。G1イニシアティブ「NEXTOKYOプロジェクト」のメンバーを中心に、産業、文化、ライフスタイル、政治などの視点から、クリエイティブシティTOKYOの未来を徹底的に議論する。
ビッグデータやIoTの大波は農業の世界を根底から変えつつある。センサー技術やデータ解析によって、これまで天候や属人的な技術に依存せざるを得なかった領域に、飛躍的なイノベーションが生まれつつあるのだ。テクノロジーの進化は、日本の農業が直面する高齢化や後継者不足による農業就業人口の減少といった問題解決の切り札となり得るのか。アグリテックの最前線で活躍する第一人者たちが語る。
ロボットやAIが人間の仕事を奪うことに対する拒絶反応が激しい欧米と異なり、世界最速で少子高齢化が進み現役世代が減少する超人手不足の日本では「ネコの手も借りたい」ならぬ「ロボの手も借りたい」状況のため、ロボットアレルギーがなく、AI、ロボット、IoTの進化による「変革」が着実に進んでいる。人口減少問題の打開策がない状況が、逆にロボットとAIによる経済成長の反転攻勢のチャンスとなるのか。第一線の専門家たちに未来を聞く。
安倍首相は今期の通常国会は「働き方改革国会だ」と語った。労基法改正を見据え、従業員のモチベーションを上げ生産性を向上させる「真の働き方改革」に成功している組織では、具体的にどう変革したのか。働き方改革を企業業績だけでなく、地方自体の魅力向上につなげ、地方創生の武器とするには。フリーランスやパラレルといった多様な働き方の展望など徹底的に議論する。
いよいよ2020年もすぐそこまで近づいてきた。残された2年を最大限有効活用し、スポーツ立国を実現するためにはスポーツに経営の視点を入れ込むことが欠かせない。スポーツと経営、ガバナンスの融合によって、プロリーグが活性化し、ファンの生態系が生まれる。オリンピアンたちとスポーツビジネスの最前線を行く経営者がスポーツの未来に新たなケミストリーを生む。
マイナンバー制度がスタートして2年。昨年11月にはマイナンバー制度に基づく「情報連携」と個人向けポータルサイト「マイナポータル」の本格運用がスタートしたが、国民の理解はそれほど進んでいない。今後つながるであろう個人の医療情報や金融情報との連携でマイナンバーが社会、働き方、人々の生活、行政をどう変えるのか。マイナンバーによって行政が持つビッグデータの活用が進めば、その影響力は計り知れない。テクノロジーの進化から取り残されがちな行政の分野におけるイノベーションの可能性をトップランナーたちが語る。
仮想通貨を使った新たな資金調達方法としてICOがその利便性、コストの低さから爆発的な広がりを見せ始めている。一方、世界ではICOの投機性を危惧し、中国政府は早々にICOを全面禁止とし、米国やロシアも規制強化に乗り出している。フィンテックの分野で世界に後れを取る日本だが、健全な市場の成長のために何をすべきなのか。日本が取るべき方策をキーマンたちが語る。
地方創生には何が必要か。100の行動では、(1)よそ者、若者、バカ者の活用(ベンチャー・NPO)(2)徹底的な規制緩和による楽市楽座(農林水産業)(3)外部からの積極的な投資による産業の植生(工業)の3つを挙げた。実際、水戸では「水戸ど真ん中再生プロジェクト」が主体となり、よそ者を呼び、規制緩和を行い、外部からの投資を呼び込んで、それまで空き地だった市街地広場を「まちなか・スポーツ・にぎわい広場(M-SPO)」としてアリーナとカフェを中心としてスポーツと食が楽しめる場所に変貌させた。地方創生のキーマンたちが現場の景色を語る。
さまざまなテクノロジーの融合が一層進むクロステックによる革命は、人々の生活、産業、社会そして地球環境をも劇的に変えていく。これからの世界において日本が取り残されないためには、次の世界をつくるテクノロジーに集中投資し、変革を先取りしていくことが必要だ。日本が世界に勝つための方策と行動を議論する。
次の10年。世界の変化のスピードはますます速くなっていく。日本が変化に取り残されるのではなく、変化の最先端に居続けるために今何をすべきか。初日のナイトセッションで議論された新たな「行動」を各グループより発表してもらい、全体で議論する。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2018年02月10日(土)〜2018年02月12日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1 |
英国の欧州連合(EU)離脱、米国新政権の誕生により、戦後70年間かけて先進国が構築してきた世界秩序は根底から変わろうとしている。孤立主義が広がり、各国は保護主義政策を掲げ、自由貿易や安全保障もまた、その枠組みの見直しを迫られている。「Gゼロ」の時代において、世界の模範となる日本を実現するために、いま何が必要か。世耕経済産業大臣、竹中平蔵氏が議論するこの国の未来。
英国の欧州連合(EU)離脱、米国トランプ政権の誕生。第二次世界大戦後、70年間かけて欧米が築いてきた世界秩序は、大きくその枠組を変えようとしている。米国が、自国第一主義・孤立主義・保護主義に進む中、米国一強体制は終焉し、世界はリーダー不在の「Gゼロ」の時代を迎えようとしている。世界を支配する新たな秩序とは何か。世界の模範たるために、日本が果たすべき役割を議論する。
すべてのものがインターネットでつながり、蓄積されるビッグデータが指数関数的に増大する中、人工知能はもはや一過性のブームではなく、産業構造を根底から変革しようとしている。医療や金融、法曹をはじめ様々な領域で実用化が進み、自動車や飛行機といったハードウェアがネットワークにつながれ、データは21世紀の石油となりつつある。人工知能の進化がもたらす新たなパラダイムにおいて、企業経営はどのようにその形態を変えるのか。新たな産業の枠組と競争優位の構築を議論する。
ロボットや人工知能、IoTといったテクノロジーの進化は、リテール・流通業界を大きく変えようとしている。2016年末にはAmazon Dash Buttonが日本に上陸し、ドローンを利用した配達の実証実験が進む。物流と消費者動向が大きく変わる一方、小売各社はいち早くオムニチャネル戦略を推進し、リアルな店舗とネットの融合が進みつつある。10年後、「買い物」はどのような姿になるのか。コマース革命の鍵を握る経営トップたちが描く流通の未来。
2016年5月、現職のアメリカ大統領として初めてオバマ氏が広島を訪問。8月には安倍昭恵内閣総理大臣夫人が真珠湾を訪れ、12月には安倍首相がオバマ氏とともに真珠湾で犠牲者への祈りを捧げた。戦後70年を経て、両国が過去に向き合い、宰相たちが手を携えた姿は、世界にどのように映ったのか。経済のブロック化が進み、テロと復讐の連鎖が広がる世界において、日本が世界の模範となるために、発信すべきメッセージを考える。
2020年の大学入試改革を前に、テクノロジーの進化によって、学校教育の現場もまた大きく変わろうとしている。反転教育やMOOCが普及し、スマホを活用した授業やアクティブラーニングなど学び方の多様化が進み、角川ドワンゴによるN高やLITALICOのように様々な形態の教育が生まれつつある。技術革新が知識という概念さえ変容しつつある中、これからの時代を生きる子どもたちに、どのような能力が必要となるのか。教師や学校という場の果たす役割はどのように変わるのか。教育界のキーパーソンたちが議論する。
千数百年の時に磨かれてきた日本の文化・アートは、伝統と革新を繰り返し、大きな価値を生み得る潜在資産となった。その力を解き放ち、世界の土俵で本来あるべき評価を勝ち取る。さらに、日本の地域創成やソフトパワー強化につなげる。そのために、我々がなすべきことは一体何なのか。室町以来の立花の源流を継ぐ池坊次期家元。江戸初期、裏千家始祖の仙叟宗室に同道して以来、金沢で伝統と革新を繰り返してきた大樋焼十一代。そして、日本の芸術を広く知らしめるため、「開運!なんでも鑑定団」にも出演する思文閣のトップ。それぞれの場で、重層的な文脈を踏まえながら、自らの道を築いてきたメンバーが、「いま」のための本質を議論する。
「2026年までに銀行はなくなる」――ロシア貯蓄銀行のVPアンドレイ・シャロヴィ氏はそう予言した。かつて銀行の支店が行なっていた業務は、いまやスマートフォン一台に代替されつつあり、メガバンクや大手生保はFintechベンチャーとの連携を加速し、新たな金融ビジネスの構築を進めている。テクノロジーの進化は金融にどのような変化をもたらすのか。新たなデファクトスタンダードに向けて各国が覇権を競う中、とるべき戦略をFintechのキーパーソンたちが議論する。
戦後70年かけて築かれた国際社会の枠組は大きく変わりつつあり、新たな秩序の形成に向けて各国が動く。外交におけるアジェンダ・セッティングとルール・メイキングのプロセスの重要性はますます高まり、国際機関での発信力をはじめとするレジティメート・パワーの獲得が急務となっている。リーダー不在の「Gゼロ」の時代において、日本が世界の模範たるために、どのようなイニシアティブをとるべきか。新たな秩序に向けた役割と行動とは。
英国の欧州連合(EU)離脱、米国大統領選は、社会の大きな分断をあらわにする結果となった。地方と大都市、若年層と高齢者層、知識層と労働者層――急激なグローバリゼーションは経済格差をもたらし、中間層の衰退によって二極化が進み、社会の断絶が生まれている。激動の中、日本が世界の模範たる堅固な社会をつくるためにとるべき行動とは。
2016年参院選を経て、衆参両院で憲法改正案の発議が可能な改憲勢力が形成され、改正の是非から、どのように改正するかという議論が本格化している。公布から70年を迎えた日本国憲法の改正はどこへと向かうのか。国際政治学者の三浦瑠璃氏、与野党の気鋭の政治家を迎えて議論する。
都市と地方、政府とNPO、個人と共同体――様々な関係が見直される中で、新たな社会をどのようにデザインするのか。俳優として、リバースプロジェクト代表として、教育や芸術など様々な活動をデザインし実行する伊勢谷友介氏、ニューヨーク大学やバッファロー植物園、セネガルの芸術村など世界の建築シーンで活躍する森俊子氏を迎えて語る。
2012年に誕生した第三世代のゲノム編集技術「クリスパー・キャス9」は、生物学の研究や開発方法を劇的に変えつつある。正確な遺伝子操作が極めて簡単に行えるようになり、ゲノム編集ツールはインターネット上で安価に売買されるようになった。医療分野においては、iPS細胞とゲノム編集を組み合わせた研究が始まり、農作物やエネルギー分野においても、実用化に向けた研究が進められている。ゲノム編集は、人類にバラ色の未来をもたらすのだろうか。中国によるヒト受精卵のゲノム編集が発表される中、新たな技術にどのように向き合っていくべきか。ゲノム編集の最先端をキーパーソンたちが語る。
2016年末、「正社員の副業後押し」の見出しが新聞の一面トップに躍り、副業容認に向けた政府指針が報じられた。ロート製薬は昨年いち早く副業解禁を打ち出し、ヤフーは4月から一部週休3日制を導入する。クラウドソーシングの普及によって、企業や場所にとらわれない多様な働き方が生まれ、上限日数制限のない在宅勤務制度を導入する企業も増えている。人工知能やロボットの技術革新が進む中、より高い生産性を実現するために、企業はどのような人材戦略をとるべきか。一億総活躍社会の実現に向けた働き方と労働法制を考える。
リオ・デ・ジャネイロ・オリンピック閉会式でのフラッグハンドオーバー・セレモニーは世界を魅了した。東京オリンピック・パラリンピックまで3年、開催に向けて国内の機運も高まりつつある。2020年、そしてその先に向けて、後世に引き継がれるオリンピック・レガシーを残すために、どのような取組が必要だろうか。都市、そして国家のグランドデザインを実現するための行動を議論する。
2016年11月、自民党の経済構造改革に関する特命委員会が提言の中間報告案をとりまとめた。地域中核企業の支援政策と第4次産業革命の推進を掲げ、日本再興戦略改定への反映を目指す。テクノロジーの進化によって、産業や社会の枠組みが大きく変わりつつある中、名目GDP600兆円を実現するために必要な成長戦略とは何か。地域活性化のキーパーソンたちと気鋭のエコノミストを迎え、特命委員会の事務局長代理を務める平将明氏とともに議論する。
18世紀の産業革命によって黎明を迎えた資本主義は、テクノロジーの指数関数的な進化によって変容しつつある。コミュニケーション・エネルギー・輸送の形態が進化し、所有や富の概念すら変わりつつある時代において、交通や雇用、都市といったインフラもまた変化に直面している。人工知能とロボットが発達する未来、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会をどのようにデザインするべきか。デザイン・バイオテクノロジー・人工知能の第一人者たちが描く未来の共同体。
富の格差と社会の二極化が深刻化する一方で、「包括的」資本主義という概念が生まれつつある。またGPIFの国連責任投資原則への署名をきっかけに、国内でもESG(環境・社会・ガバナンス)を投資の判断に取り入れる機運が急速に高まっている。多くの弱者を生み出す資本主義から、投資家に利益を還元しつつも、富を広く社会に広める新たな資本主義を世界中が模索している。従来の富の競争から取り残されてきた人々を包摂する資本主義は、果たして実現可能なのか。持続的な企業価値向上と資本市場の効率化を両立する新たな金融システムのあり方を議論する。
2015年、東京都渋谷区で日本初となる「同性パートナーシップ条例」が施行された。セクシュアル・マイノリティが自分らしく生きることを支援するイベント「東京レインボープライド2016」には、過去最多となる7万人超が参加し、LGBTへの社会的関心や理解が進む一方で、無理解に基づく偏見や差別もいまだ根強い。自民党内では「性的指向・性自認に関する特命委員会」が発足し、LGBTの超党派議連が会合を重ね、セクシュアル・マイノリティ支援に向けた法案成立を目指す。すべての人々がジェンダー・アイデンティティを確立し、多様性を受け入れる組織や社会を実現するために、とるべき行動を考える。
脱東京一極集中が叫ばれる中、画一的な地方行政から、独自の強みを活かした地域経営の取組が各地で進められている。政官民の枠組みを超えたコラボレーションが増える一方で、同床異夢となるケースも後を絶たない。自治体と企業の協業を成功させる“ツボ”とは何か。G1首長ネットワーク、G1発のイニシアティブである熱意ある地方創生ベンチャー連合のメンバーたちが議論する。
インターネットがあらゆるビジネスモデルを根底から変え、業界の「壁」が消滅しつつある。知能は人工知能・クラウドにつながれ、メディアやコミュニティは変容し、経済活動が宇宙に拡大する時代。新たなイノベーションが生みだす次の「稼ぐ仕組み」とは何か。誰がつくるのか。異才たちの世界観と次なる一手とは。
現在日本で稼働している原子力発電所は川内や伊方などごくわずかである。化石燃料輸入に依存したエネルギー政策は貿易収支を悪化させ、電力会社の業績の大きな圧迫要因となっている。化石燃料により排出されるCO2は、地球環境を悪化させている。固定価格買取制度によって太陽光発電は増加したものの、電力料金は上昇の一途を辿る。持続可能な成長を実現するエネルギーミックスとは何か。その社会的コンセンサスを得るための方法論とは何か。エネルギー政策のキーパーソンたちが議論する。
ヒラリー・クリントンの圧勝を予想したニューヨーク・タイムズが、トランプ次期大統領の当確を報じるまでに長い時間はかからなかった。多くの大手メディアや調査会社が情勢を見誤る一方、ソーシャルメディアが大統領選において果たした役割が検証されつつある。トランプの娘婿であるクシュナー氏は、大統領選のメディア戦略において、ソーシャルメディアを主要ツールとしたが、Facebook上で共有された偽ニュースの影響も指摘されている。ソーシャルネットワークでつながれた無数の声が世論を形成する時代、これからのメディアが果たすべき役割、政治・企業・個人がとるべきコミュニケーション戦略を考える。
2017年度予算案では、社会保障費は過去最大となる32兆円台が計上される見通しとなり、1970年には歳出の15%に過ぎなかった社会保障費は、いまや一般会計の3分の1を占める。昨年には患者申出療養制度が創設されたが、混合診療の拡大には、いまだ多くのハードルが立ちはだかる。高齢化が進む日本において、財政の健全化を実現し、競争力ある医療を生み出すための行動を考える。
日本のポップカルチャーも伝統文化も、世界で既に広く消費されている。新たな切り口で発信力を高め、日本文化の価値再創造と革新につなげるにはどうすべきか?70年代以降の日本文化をテーマに、ポンピドゥー・センター・メス(パリ)で展覧会を行うキュレーター長谷川氏。今の日本を世界に伝える「MORE THANプロジェクト」で、中小企業とプロデュースチームの協働を支援するロフトワークの林氏。地域密着型のシティガイド「タイムアウト」で、日本の街とコンテンツを世界に発信する伏谷氏。第一人者たちが、キュレーションによる文化発信の真髄を議論する。
2016年11月、国内初となる宇宙活動法が制定された。「宇宙活動法」と「衛星リモートセンシング法」である。かつて国家・大企業主導で進められてきた宇宙開発プロジェクトは、いまや民間主導型のイノベーションが加速し、米国やルクセンブルクをはじめとする世界各国が宇宙資源開発の産業化を進めている。最後のフロンティアとされる宇宙において、巨大な産業が生まれつつある時代、世界の模範たる日本が果たすべき役割とは何か。法案成立に尽力したG1宇宙研究会メンバーたちが議論する。
北海道の食料自給率は207%を超え、広大な自然や食といった観光資本は人々を魅了し、北海道を訪れる外国人観光客は10年間で約3倍に増加した。一方で、急激な人口減少や高齢化によって、生活インフラは見直しを迫られ、財政状況悪化に直面する自治体は、厳しい舵取りを迫られている。北海道の持つポテンシャルを活用し、持続可能な産業構造を実現するために必要な行動を議論する。
2016年9月、Bリーグの開幕戦に日本中が沸いた。2つのリーグは新たなリーグとして生まれ変わり、テクノロジーを駆使したアリーナならではのエンターテイメント体験に観客や視聴者は魅了された。スポーツと経営、ガバナンスの融合によって、プロリーグが活性化し、ファンの生態系が生まれる。熱狂の裏には、優れたマネジメントがあり、スタジアムやアリーナを活用した新たなビジネスやコミュニティが生まれつつある。スポーツの持続可能な発展の実現に向けたプロリーグ経営者たちの行動とは。
北朝鮮による日本海への弾道ミサイル発射が相次ぎ、中国は東シナ海・南シナ海での活動を活発化させ、アジア太平洋地域の安全保障は喫緊の課題となっている。米国の孤立主義が明確になり、在日米軍の再編が進み、日米同盟もまた新たな局面を迎えようとしている。到来するGゼロ時代において、日本がとるべき防衛政策を議論する。
原始の時代から人々の感覚を揺り動かしてきた音楽は、時代の変遷やテクノロジーの進化によって、その表現を変えてきた。人類が月面を駆け、ソーシャルメディアが情報の伝播を変え、バーチャルリアリティの進化が人間の認知を変容していく時代、未来の音楽はどのように生まれるのだろうか。サカナクション山口一郎氏、初音ミク生みの親である伊藤博之氏が語るミュージックシーンの普遍と革新。
地方創生政策の積極的な推進が功を奏して、有効求人倍率は史上初めてすべての47都道府県で1倍を超えた。一方で、人口減少が急激に進む中、地域経済が直面する課題はなお山積みとなっている。少子高齢化が進む中、社会インフラを見直し、自律的かつ持続的な力強い成長戦略を実現していくために、いま何が必要なのか。自治体・企業・政府が三位一体となって取り組むべき行動を議論する。
人工知能、ロボット、iPS細胞、宇宙の領域において、事業化と競争優位の構築を実現することを目的に発足した「G1テクノロジー研究所」。「魔の川、死の谷、ダーウィンの海」を乗り越えて、日本のテクノロジーが世界の模範たることを目指して、現在では「G1宇宙研究会」「G1ディープラーニング研究会」「G1 Fintech研究会」が発足している。日本が研究・事業化の分野において、世界で勝てるための方策とは何か。科学技術分野で、世界模範たる日本を実現するための行動を議論する。
戦後70年間築いてきた枠組は崩壊しつつあり、世界は新たな秩序を模索している。混迷する時代に、「世界の模範となる日本」をつくり上げていくために、我々はいま何をするべきなのか。初日のナイトセッションで議論された新たな「行動」を各グループより発表してもらい、全体で議論する。G1が実現する100の行動!
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2017年03月17日(金)〜2017年03月20日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
(オプション・別途お申込が必要です)
(オプション・別途お申込が必要です)
(オプション・別途お申込が必要です)
第1回目のG1サミットのテーマは「2020年の日本と世界」であった。7年が経過し、2020年に東京オリ・パラ開催に向け準備が進み、日本のビジョン「100の行動」が出版され、G1世代が日本の中心に位置する。日本の政治経済の中枢にいる世耕官房副長官・竹中教授の両氏に日本の現況を聞いた上で、2020&Beyondの未来、そして僕らがとるべき「100の行動」に関して議論する。
かつて日本の六重苦として挙げられた課題のうち、今なおほぼ手つかずのまま残るのは、労働問題のみだ。安倍政権は雇用・農業・医療を「岩盤規制」と呼び、制度改革を進めているが、抜本的な改革に向けて、なお多くの課題が残されている。G1が本腰を入れてこの問題に取り組むべく、河野規制改革担当大臣、民主党の細野政調会長を交えて、全体会でこの問題に取り組む。
2015年6月の公職選挙法改正により、選挙権年齢は70年ぶりに見直され、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。もうひとつの参政権である被選挙権についても、年齢引き下げの機運が高まっている。G1 COLLEGEから始まったイニシアティブである「被選挙権年齢引き下げ」は2016年2月、記者会見を行い、学生代表らが声を上げた。政界与野党のキーパーソンたちが議論する。
テクノロジーの進化はあらゆる業界をディスラプトし、社会構造が根底から変わりつつある。今後10年間、どのような市場が新たに生まれ、我々を取り巻く世界はどのように姿を変えるのか。イノベーションを生み出し、新たな市場を創造する起業家たちの目には何が見えているのか。テクノロジーがもたらす未来とベンチャーの最新潮流を語る。
2020年に向けて東京のグランド・リ・デザインが急速に進められている。多様な価値観が融合し、異質な文化との出会いが生み出すクリエイティビティが都市競争力に直結する。デジタルアートを通じて都市に住む人々の関係性をデザインする猪子寿之氏、ニューヨークを拠点に活躍する建築家・森俊子氏、弁護士として風営法改正によるクラブ深夜営業の解禁に尽力した齋藤貴弘氏をパネリストに迎え、「NeXTOKYO Project」を主宰する梅澤高明氏と共に議論する。
2016年の伊勢志摩サミット、2020年の東京五輪の開催をマイルストーンとして、今年10月にスポーツ文化ワールドフォーラムが開催される。日本が育んできた独自の文化資本を普遍的な価値として世界に発信していくために、どのような取組が必要だろうか。「日本遺産」を創設した下村前文科大臣を交えてG1メンバーと議論する。
優雅な衰退から力強い成長へ。安倍政権は、民間の活力を最大化することを目的に、国家戦略特区を推進してきた。だが、医療や農業、雇用といった岩盤規制のみならず、ドローンやセグウェイ、民泊といった新たな産業やテクノロジーの前に、しばしば規制や既存権益が立ちはだかり、イノベーションを阻害する要因となってきた。既存産業のアセットを守りながら、新たな成長を実現していくために必要な打ち手とは何か。特区における成功事例を全国に広げていくために、求められる次の一手とは。
インターネットの出現があらゆる業界をディスラプトしていく中、金融業界も大いなる岐路に立っている。ダボス会議では、銀行が無くなる日を真剣に金融業界のトップが議論していた。ブロックチェーン技術の応用、ビットコインなどの出現、ロボアドバイザーによる運用の普及––情報技術の進化や人工知能の出現によって、金融業界の構造が根底から変わりつつある。Fintechの進化は、どのようなビジネスを生み出すのか。経済のあり方をどのように変えていくのだろうか。日本企業・行政はどう対応すべきか。
2016年1月には北朝鮮が「水素爆弾実験」の成功を発表し、翌2月には弾道ミサイルの発射が行われた。中国は南シナ海に人工島の造成を進め、周辺国が領有権を巡って対立。東シナ海では尖閣諸島問題で日中間での緊張が続いている。激変する国際情勢の中で、東アジアの安全保障をどのように考えるべきか。日本のとるべき外交と安全保障政策を議論する。
「100年後の沖縄を黒木の杜でいっぱいにしたい」という思いで「くるち(黒木)の杜100年プロジェクトin読谷」を2012年に発足した宮沢和史氏。2000年から公演数270回・観客動員数15万人を超える中高生の舞台「現代版組踊 肝高の阿麻和利」で舞台を通した人づくりのメッカ勝連町(現うるま市)を生んだ平田大一氏。子供たちが地域を学び、地域に誇りを持つことが、地域を変え日本を変える力となる。次世代、さらに次の世代へ、、100年後の沖縄を共創する両氏が語る”沖縄発”地域おこし・人おこしのカタチとは。三線を片手に沖縄の未来・日本の未来を語る。
2016年4月に創設される患者申出療養制度は、混合診療拡大の嚆矢として、岩盤規制といわれる医療分野に風穴を開ける大きな一歩となる。安倍政権発足後、健康・医療分野の様々な改革が矢継ぎ早に実現されている。しかし国民医療費はついに40兆円を超え、財政圧迫の大きな要因となっている。合理化を進め、国民の利便性を向上すると共に、競争力ある医療サービスを生み出していくために、どのような医療改革が必要か。行政改革・医療経営・社会保障改革の視点から議論する。
2015年10月、Google DeepMindの開発した囲碁ソフト「AlphaGo」が史上初めてプロ棋士に勝利したというニュースは、翌1月にNature誌への論文掲載と共に、大きな反響を呼んだ。チェスなどのボードゲームに比べて格段の複雑性を持つ囲碁での人工知能の勝利は、人工知能の無限の可能性を知らしめた。人工知能はどこまで進化するのか。経営や社会への応用は。人工知能の新たなフロンティアを、囲碁有段者の知の巨人たちが議論する。
2016年のG7伊勢志摩サミット開催まで2ヶ月。主要国の首脳が一堂に会するサミットは、外交の場であるだけでなく、日本の魅力を世界に発信する絶好の機会ともなる。伊勢志摩国立公園の美しい自然、古くから「御食つ国」と呼ばれた食の豊かな恵み、世界に冠たる真珠の養殖で知られる英虞湾の賢島。里海の豊かな地域資本を世界に発信し、観光都市としての持続的な成長につなげるために、どのようなサミットをつくっていくべきか。オール日本としての取組をG1メンバーが議論する。
阪神大震災、NPO法の制定を経て、いまや認証NPO法人は5万件を超え、新しい公共の担い手として、様々な社会問題の解決に取り組んでいる。しかし米国ではNPO上位15団体が10億円を超える収益を上げる一方で、日本のNPOは規模が小さく、1億円以上の収入があるNPO法人は130程度に過ぎない。多くのNPOは資金難を抱え、働く人々の報酬も十分とはいえない。大きな社会的インパクトを生み出す組織をつくり、持続可能な経営を実現するために、どのような改革が必要だろうか。政治・行政・NPOのキーパーソンたちが議論する。
テクノロジーの進化は教育を根底から変えようとしている。政府は2020年までに小中学校の生徒に一人一台の情報端末を配布する目標を掲げ、ICT化を推進している。グローバル化が進み、人工知能をはじめとする技術革新が進む中、これからの時代を生きる人たちに必要な資質とは何か。教育再生のキーパーソンたちが議論する学校教育の未来。
GoogleやFacebook、トヨタ、リクルートといった企業が人工知能技術の研究・開発に次々と参入し、あらゆる産業の構造を大きく変えようとしている。インターネット上に蓄積された膨大なデータと人工知能の解析技術が融合することによって、どのようなビジネスが新たに生まれるのか。いまや技術的なブレイクスルーを超えた人工知能の発展は、我々の生活や社会にどのような変革をもたらすのか。人工知能が変えるビジネスと来たるべき社会の姿を議論する。
中国発の世界同時株安で幕を開けた2016年。1月4日には中国市場で株価が7%あまり下落し、サーキットブレーカーが発動された。貿易額はリーマンショック以来6年ぶりに前年割れとなり、2015年では前年比8%減となった。中国でいま何が起きているのか。中国の景気減速は世界経済にどのような影響をもたらすのか。中国の現状を知悉するキーパーソンたちが語る。
保護者のいない子ども、虐待を受ける子どもたちを里親や施設が養育する社会的養護。その対象児童は約4万6千人にのぼるが、日本ではその9割が施設に引き取られ、里親に引き取られるのは1割である。厚生労働省は今後10数年で里親委託率を30%にする目標を掲げるが、その目標でさえ先進国の中で最低水準にある。G1サミットから始まった「子ども」イニシアティブでは、自治体と民間企業による「官民子ども協議会(仮)」を設立し、養子縁組・里親委託を始めとする家庭養護の推進に乗り出した。すべての赤ちゃんが家庭で暮らせる社会を目指して、官民が取り組むべき行動をイニシアティブメンバーらが議論する。
東京一極集中から脱却し、地域ならではの特色を生かした地方創生が進められる中、各地域の強みや弱みを正確に把握し、定量的な分析に基づいた政策立案の重要性がますます高まっている。政府は「地域経済分析システム(RESAS)」を立ち上げ、人口動態や産業構造、人の流れといったビッグデータを集約し提供している。勘と経験の行政運営から、可視化されたデータに基づいた戦略的行政へ。ビッグデータを活用した地方創生の次の一手を議論する。
製造現場における産業用ロボットの普及が進み、人型ロボットはいまや生活の中で身近な存在となりつつある。人工知能やIOTの技術革新によって、ロボットは生活のあらゆるところに存在するようになり、産業・医療・福祉・教育・コミュニティ、あらゆるシーンが変革されていく。ロボットは、人間の未来をどのように変えるのか。人とロボットが共生する社会とは。限りなく人間に近いアンドロイドの開発で知られる石黒浩氏、パーソナルモビリティ「ILY-A」の生みの親である古田貴之氏を迎えて議論する近未来。
2015年10月の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)大筋合意によって、農林水産物の輸出拡大が期待されている。安倍政権は農業を成長戦略のひとつに位置づけ、2020年までに農林水産物・食品の輸出額を1兆円に拡大する目標を掲げる。日本の農業は国際競争力ある産業となり得るか。農業が競争力ある産業となるために必要な改革とは何か。高齢化・後継者不足に直面する国内農家が生産性を向上し「稼げる農業」を実現していくために、どのような「攻め」と「守り」の打ち手が必要なのか。農業改革に向けた行動を議論する。
地方都市の空洞化問題が深刻化する一方で、活性化に向けた民間主動のイニシアティブが各地で生まれている。ストライプインターナショナル石川康晴氏は「中山間地域活性化プロジェクト」を提唱し、クールオカヤマフェスやオカヤマアワードを通じて、瀬戸内の地域振興を推進する。グロービス堀義人は「水戸どまんなか再生プロジェクト」を立ち上げ、民間主導による水戸市の中心市街地活性化を進める。民間主動のイニシアティブは地方創生の起爆剤となるのか。企業と自治体の協働による新たなまちづくりの形を、伊原木岡山県知事を交えて議論する。
2015年9月に成立した安全保障関連法の審議においては、集団的自衛権行使の合憲性を巡って世論が大きく分かれた。安倍政権は今夏の参院選で憲法改正を争点に掲げることを明言している。69年間に亘って一度も改正されなかった日本国憲法は、改正に向けてようやくその一歩踏み出すことになる。激動する国際情勢の中で、憲法条文の何を残し、何を変えるべきなのか。与野党の若手政治家と若者代表知識人達が議論する。
山中伸弥教授のノーベル賞受賞から3年余。再生医療の実用化に向けた臨床研究が進み、法整備が進められ、企業の参入が相次いでいる。2015年4月には武田薬品工業が京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と提携し、200億円の研究資金を投じてiPS細胞を使った創薬・治療の共同研究に乗り出すことを発表した。阪大の澤芳樹教授は世界で初めて細胞シートを使った心筋再生医療に成功。理化学研究所はiPS細胞からつくられた網膜細胞の移植手術に成功した。熾烈な国際競争が繰り広げられる中、世界に先駆けて再生医療の実用化・産業化を実現するために、何が必要なのか。山中伸弥教授、澤芳樹教授が議論する再生医療の未来。
国際機関は、外交の最前線である。だがその国際機関において、日本は大口出資国・費用負担国であるにもかかわらず、アジェンダ・セッティングとルール・メイキングにおいて存在感、影響力、リーダーシップが発揮されていない。日本のプレゼンスを向上させ、世界に貢献していくための行動とは何か。塩崎厚生労働大臣を迎え、MIGA、WTO、WEFで活躍する日本人リーダーたちが森まさこ元大臣を交え議論する。
2015年1年間に日本を訪れた外国人客は過去最高の1973万人となり、2020年までの目標としていた年間2000万人がほぼ達成され、2020年の訪日観光客数の目標は3000万人に引き上げられた。円安を背景とした訪日観光客の増加を一時的な機運とせず、観光を持続可能な競争力ある産業としていくために、次に必要な打ち手とは何か。インバウンドの数の「次」に何を目指すのか。2020年に向けた観光の構造改革を議論する。
人工知能、ロボット、iPS細胞、宇宙の領域において、新たなビジョンを描き、行動していくことを目的として、「G1テクノロジー研究所」が昨年末に発足した。「魔の川、死の谷、ダーウィンの海」を乗り越えて、日本のテクノロジーが、基礎研究から応用研究、商品化、そして事業化まで世界で勝ち続けることができるのか?その方法論を前文部科学大臣、ノーベル賞学者とともに議論する。
「2020年のより良い日本と社会をつくろう」――その一言から立ち上がったG1サミットは8年目を迎えた。G1から生まれたイニシアティブは、いまや様々な領域で日本を変革しようとしている。2020年、そしてその先の日本をつくるために、リーダーたちがとるべき行動とはなにか。G1の新たなビジョンと行動を議論する。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2016年03月18日(金)〜2016年03月21日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
修験道発祥の地である奈良県大峯山。1300年の歴史の中で、ただ二人目となる大峯千日回峰行と四無行を満行し、仙台・秋保の地に慈眼寺を開山した塩沼亮潤大阿闍梨。往復48キロの山道を毎日16時間かけて歩き、断食・断水・不眠・不臥を9日間続ける苦行を経て、見えた世界とは何か。秋保でのG1サミット開催に向けた特別講演。
2008年をピークに人口減少に転じた日本は、これから本格的な人口減少社会・超高齢化社会に直面する。日本が向かうのは、新たな形の発展か、それとも衰退なのだろうか。その中、「人口1億人を維持する」方針が、「選択する未来委員会」から提示された。人口減少社会を食い止め、継続的に成長するためには、出生率の向上、さらには移民の検討が大きな課題となるであろう。「選択する未来」委員会の会長を務めた三村明夫氏、同委員の石黒不二代氏、長年にわたり規制緩和を推進してきたオリックス宮内義彦氏が、困難な問題に真正面から議論する。
東日本大震災で甚大な被害を受けた東北沿岸部各地で進められる復興計画。被災3県で整備予定の防潮堤は総延長386キロに及ぶが、防災効果、景観や生態系保護の観点から、計画を懸念する声も上がっている。宮城県女川町では、復興計画において防潮堤をつくらないことをいち早く決定した。町民の合意形成によって、海と共に生きることを選び、居住地の高台への集約を進めている。人口減少社会において、魅力あるまちづくりと、災害に強い都市計画を両立するための解はどこにあるのか。長く受け継がれてきた土地の資産を活かし、自然と共存していくために、どのようなまちづくりを進めていくべきだろうか。日本全体が直面する問題に、先進的に取り組む被災地の事例から考える。
インターネットやスマホが普及する中で、新たなサービスの生態系が生まれ、起業家たちがビジネスを通じて世界を変えていく―――。だが、インターネットでの競争は、世界の強者との戦いでもある。覇者にならないと、失敗を意味するに等しい。レシピ検索サイトで、月間利用者数が5000万人を超え、日本の料理シーンを変えつつあるクックパッド、スマートフォン向けアプリが累計1億ダウンロードを突破したコロプラ、3年で日本を代表する経済メディアを目指す「NewsPicks」を運営するユーザベース。各社を率いるリーダーたちが描く「インターネットで覇者になる戦略」とは。
2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、原子力発電所の再稼働の方針が明記された。しかし将来的な電源比率については、今後の課題として残されている。東日本大震災後、日本のエネルギー自給率は6.0%まで落ち込み、化石燃料への依存増大は国富の流出を招き、2013年には過去最高となる11.5兆円の貿易赤字を記録した。原油供給が中長期的に逼迫し、温室効果ガスの排出増大が懸念される中で、世界のエネルギー情勢もまた、大きな変化に直面している。安定的なエネルギー供給を確保し、持続的な経済成長を実現するために、日本が取るべきエネルギー・ミックスとは何か。その実現に向けて、どのような点を考え、実現していくべきか。国家戦略としてのエネルギー政策のあり方を議論する。
人工知能が急速な進展を遂げている。コンピュータの扱うデータ量が爆発的に増加し、さらにディープランニングによって自分自身で学習できるようになった人工知能は、技術的なブレークスルーを超え、ホーキング博士やイーロン・マスクが人類への脅威を唱えるまでとなった。人工知能はどのような可能性を秘めているのか。ロボットやIOT(モノのインターネット)とつながることによって、我々を取り巻く生活やビジネスは、どのように変わるのか。はこだて未来大学学長であり人工知能学会フェローを務める中島秀之氏、世界屈指の人工知能であるIBMのWatsonを担当する中林紀彦氏、人工知能とWEB工学の研究で知られ、ドワンゴ人工知能研究所客員研究員に就任した松尾豊氏。人工知能のキーパーソンたちが議論する。
2020年の東京五輪開催に向けて、スポーツ振興の機運が一層高まり、各スポーツ界で選手強化活動が進められている。一方で、日本バスケットボール協会が国際バスケットボール連盟(FIBA)から無期限の資格停止処分を受け、東京五輪への出場が危ぶまれている。この数年間、内閣府が公益社団法人に警告を出した5団体のすべてがスポーツ団体であり、テコンドー協会は公益社団法人の返上を決めた。選手の競技力向上のみならず、選手が活躍できる環境をつくり、ファンを呼び、競技を活性化するために、どのような体制が必要か。2020年東京五輪開催、そして真のスポーツ振興に向けた競技と協会のあり方を議論する。
2009年の第1回G1サミット以来のメンバーであり、ボードメンバーである山中伸弥氏が、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞。iPS細胞は、難病治療・再生医療の大きな可能性を秘め、世界中から期待と注目を集めている。一方で実用化に向けては、莫大な資金力を持つ米国はじめ各国が参入し、熾烈な国際競争が繰り広げられている。「iPS細胞を患者のベッドサイドへ」--実用化に向けた道のりと課題、政官民が取り組むべき行動とは何か。
中国の台頭によって、東アジアにおけるパワーバランスに大きな地殻変動が起こっている。南シナ海の領有権を巡って、フィリピン・ベトナムとの対立が続き、尖閣諸島問題では、日中間での緊張状態が続いている。米国がリバランス政策へと舵を切る中、中国の海洋進出に対して、日本は今後、米国、そしてASEAN諸国との協力の枠組みをどのように構築していくべきだろうか。キーパーソンたちが東アジア外交と日本の進むべき方向を議論する。
日本企業を取り巻く「6重苦」(円高・法人税・労働規制・環境制約・FTAへの対応遅れ・電力問題)は、少しずつ改善の方向に向かっているものの、労働規制はなお、日本経済の成長の大きな足かせとなっている。安倍政権では「働き方の改革」を成長戦略の大きなテーマとして位置づけ、雇用維持型の政策から、労働移動支援型の政策に舵を切ろうとしている。しかし労働規制緩和については、依然として反対も大きく、改革には大きな壁が立ちはだかっている。労働生産性とワーク・ライフバランスを両立し、企業の競争力向上と世界トップレベルの雇用環境を実現するために、どのような施策が必要なのか。成長戦略の実現に向けた雇用改革のマイルストーンを議論する。
ネット選挙が解禁された2013年7月の参院選では、若年層の政治参加の促進が期待されたが、投票率は52.6%と戦後3番目の低さにとどまった。今国会で成立が見込まれる公選法改正案、いわゆる「18歳選挙権」は、果たして若者の選挙参加に向けた打開策となるのか。ソーシャルメディアでの政治家と有権者のコミュニケーションが普及し、インターネット上の"声"はどのように世論を変えていくのか。マスメディアとネットメディアが変わる中で、あるべき選挙の形と今後の課題について、ソーシャルリスニングを提供するホットリンク内山氏、ネット選挙を長く推進してきた田嶋氏、松田氏をパネリストに迎えて議論する。
2011年3月の未曾有の原発事故によって、福島第一・第二原子力発電所の周辺地域は警戒区域・計画的避難区域に指定され、住民は避難を余儀なくされた。避難者・転居者の数は12万人を超え、避難勧奨の指定が解除された今も、避難世帯の内、帰還希望は2割に届かず、復興への道のりはなお遠い。今後数十年かかるともいわれる廃炉と除染作業は、しかし大きな可能性をも秘めている。世界最先端のテクノロジーが福島で研究され、集積していく中で「福島の未来」をどのように描き、実行していくべきか。福島イノベーション・コースト構想研究会メンバーの石崎芳行氏、福島県選出の森雅子氏、震災以降、福島の取材を続ける「Wedge」大江紀洋氏が、未来に向けた骨太のビジョンを議論する。
「2040年までに896の自治体が消滅する」--増田寛也氏による発表、いわゆる「増田レポート」は、各界を震撼させた。2008年をピークに人口は減少に転じ、日本はこれまで経験したことのない本格的な人口減少社会に突入する。その中で、豊かさや利便性を維持していくために、国土や都市計画もまた、大幅な見直しに迫られている。人口急減と東京一極集中を回避し、医療や交通、教育といった生活インフラを守っていくために、どのようなグランドデザインが必要なのか。地方分権の新たな形に向けて、国や自治体、企業に、どのような打ち手が求められているのか。キーパーソンたちが議論する。
宇宙技術の進化によって、衛星保有国は50カ国以上に上り、新興国や民間企業の参入も相次ぎ宇宙空間のパワーバランスは、かつての米ソ二極構造から多極化構造へと大きく変わりつつある。宇宙商業市場が拡大し、また安全保障における宇宙の役割がますます重要になってくる中、「宇宙」というフロンティアで、資源開発・安全保障・外交を両立していくために、国家としてどのような戦略を推進していくべきか議論する。
雇用形態が多様化し、クラウドやテレビ会議の進化によって、リモートワークが浸透しつつある。クラウドソーシングの普及は、通勤というスタイルさえ形骸化していく。子育てやライフスタイルに合わせて、個人が働き方を柔軟にデザインする時代。ワークスタイル・ダイバーシティは、労働力を確保し、企業の競争優位に直結する戦略となっている。企業は今後、どのような組織と働き方を設計していくべきだろうか。企業と個人の関係をどのように構築していくべきか。ワーク・ライフバランスの小室淑恵氏、リクルートマーケティングパートナーズの富塚優氏、「4時間正社員制度」など独自の制度で知られるクロスカンパニー石川康晴氏が、新たな時代の働き方を提言する。
デュアルという概念が、いろいろな世界を変えつつある。二枚目の名刺を持つ人たち。会社に属しながらも、社外の仕事を受けたりNPOを手伝ったり、クラウドソーシングで仕事する人々。ひとつの会社に定年まで勤務し、ひとつの場所に住むスタイルから、多拠点で働き、生活するスタイルが広がりつつある。経済的成功や事業規模の拡大よりも、自由やコミュニティの充実を選ぶ若者たち。シェアハウスやコワーキングスペースをはじめとする新たなシェアエコノミーが生まれ、コミュニティやワークスタイルを変革していく。価値観が変容する中で、どのようなワークライフスタイルが生まれていくのか。新たな価値観と働き方を提唱するパネリストたちが提示する未来。
東日本大震災から4年。東北の沿岸部各地には、地域を愛するリーダーたちが立ちあがり、新しい復興プロジェクトをけん引しています。G1サミットのイニシアティブとして2011年3月に立ちあがったKIBOWは、2012年2月に一般財団法人化しました。皆さんから頂いた支援金やG1・KIBOWチャリティディナーでの寄付金を原資に、それらのチャレンジを支えてきました。今回のKIBOWランチでは、支援団体のひとつである宮城県女川町の「みなとまちセラミカ工房」の女川スペインタイルの取り組みをご紹介します。また、南三陸町の生わかめロール、山元町のミガキイチゴのスパークリングワインもお楽しみいただきます。KIBOWが支える復興の確かな足音を、皆様にも感じていただけたら幸いです。
日本の農産物は、国内外で高い評価を受ける一方で、農業の担い手である農家は、高齢化と後継者不足に直面し、耕作放棄地の拡大が続いている。安心して農業に取り組むことのできるセーフティネットを整備する一方で、競争力ある農業を育て、農家の所得向上を実現するためには、どのような取組が必要なのか。岩盤規制を緩和し、農業を成長産業としていくために、必要な改革とは何か。キーパーソンたちが議論する「農業の未来」。
東京一極集中の是正が叫ばれる一方で、地域ならではの魅力と機会を活かした新たな成功事例が、各地で生まれている。政官民の枠組みを軽やかに超え、個性ある地域が、あちこちで魅力的な変革を実現しつつある。ICTの進化やLCCの普及に伴い、移動や移住が増え、「住む場所」「働く場所」を個人が選ぶ時代。住まいや働き方、ライフスタイルにイノベーションが始まる中、地方にこそ、成長のチャンスがある。地域の魅力をデザインし、ワクワクするプロジェクトを生み出し、発信していく"方法論"はあるのか。TSUTAYA図書館で官民の新たな協業モデルをつくり出した増田宗昭氏、樋渡啓祐氏に、「くまモン」を生み出した水野学氏が聞く。
2014年8月、朝日新聞は、慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏の証言を報じた自社記事が虚偽であったことを報じ、記事を取り消した。これまで慰安婦の強制連行と軍の関与を裏付けてきた記事の影響は大きい。2015年1月には「日本の国際的評価が低下し、国民の名誉を傷つけられた」として、約8700人が朝日新聞を提訴。原告団はすでに2万人を超える規模となっている。世紀の大誤報は、なぜ起こったのか。なぜ32年間にわたって放置されたのか。メディアの信頼を回復するとともに、事実に基づいた歴史認識を形成し、国際社会における信用回復を図っていくために、必要な行動を議論する。
宇宙やロボット、インターネット、時代が変遷し、人間の活動や表現の領域が広がる中で、アートはどのように変わり、あるいは普遍性を持つのか。アートとテクノロジーは、どのように融合し、新たな価値を生み出すのだろうか。時代の先端を走るクリエイタ―たちは、どのような世界を見ているのだろうか。「神の雫」「金田一少年の事件簿」など大ヒット作を世に送り出し、マンガボックスではコンテンツの新たな形を世に問う樹林伸氏、アーティストとして活躍し、史上最年少でMITメディアラボ助教に就任したスプツニ子!氏が、アートとテクノロジーの未来を縦横無尽に議論する。
暗記・詰め込み型から、多面的評価の入試へ--大学入試が大きく変わろうとしている。2021年、現在の小学校6年生が大学を受験する年に、現行の大学入試センター試験が廃止され、新共通テストが創設される。「教育立国」を掲げる安倍政権の教育改革の本丸といえる大学入試制度改革。入試(アドミッション)のみならず、教育内容(カリキュラム)・卒業(ディプロマ)の3つの方針策定を義務づけ、大学の質の転換を目指す。「課題解決能力」「企画力」「人間力」を育み、世界で活躍する人材を輩出するために、中等教育は今後、どのように変化していくべきか。教育改革を推進する下村大臣、教育再生実行会議有識者である漆紫穂子氏、同会議分科会有識者の小林りん氏をパネリストに迎え、大学改革とこの国の教育の未来を議論する。
2015年度のプライマリーバランス(基礎的財政収支)赤字半減、2020年度の黒字化を国際公約として掲げる日本。社会保障改革は、可能なのか。聖域なき歳出削減と経済成長の実現に向けて、取るべき打ち手とは何か。2020年のプライマリーバランス黒字化に向けたロードマップを議論する。
G1サミットから始まった知事・市長による「G1首長ネットワーク」。改革派の若手首長らが集い、連携し、地域からの同時多発的な改革の実現を目指す。起業特区・ビッグデータ活用・教育改革・子育て支援--各地で広がる変革の取組は、日本をどのように変えていくのか。「G1首長ネットワーク」メンバーたちが議論し、次なる一手を策定する。
コミュニケーションの重要性がますます増している。国際社会において、軍事力・経済力等のハードパワー、文化力・教育力・観光力等のソフトパワーと並び、国家の情報発信力とも言うべきコミュニケーション・パワーと、国際的人間関係から生まれるネットワーク・パワーが、国力を構成する重要な要素となる。中国・韓国の広報・ロビー活動は、現在熾烈さを増している。政府は国際広報予算を大幅に切り上げ、自民党は新型「国際放送」の創設検討を進めている。"日本”を世界に広報するために、必要な戦略を議論する。
安倍内閣が2012年末に発足後、アベノミクスを打ち出し、持続的な成長に向けた大胆な規制緩和を進め、成長戦略を加速している。医療・農業や雇用をはじめ、戦後長く守られてきた領域の自由化を推進し、教育改革や地方創生を進め、ロボットやIT、科学技術への投資を行い、健全な競争環境を整備することによって、再び「稼ぐ力」を持った国を目指す。一方で、貿易赤字・財政赤字が続いている中、2020年のプライマリーバランス黒字化に向けて、成長戦略の着実な実行が求められている。力強い成長を取り戻し、日本を再生するために、取るべき行動は何か。「100の行動計画」を通じて静かなる革命を実現し、この国の再生を果たすために、G1メンバーたちが取るべき道を議論する。
東京を世界一魅力的な都市に変えよう--前回G1サミットの参加メンバーを中心に設立された「NeXTOKYO」。都市間競争が国の優劣を左右する時代、2020年とその後に向けて、どのような東京をリデザインしていくのか。文化やクリエイティビティをキーワードに、固有の魅力を活かし、世界と価値を共創する都市づくりに向けて、チームNeXTOKYOが未来の東京を提言する。
まずは国内市場でシェアを取り、上場を目指すというスタートアップ企業の成功モデルが変容しつつある。株式非公開化の道を選び、世界市場でERPパッケージのスタンダードを目指すワークスアプリケーションズユーザー数が5億6000万人を超え、世界を率いるプラットフォーマーを目指すLINE。グローバル展開を目指すベンチャーの成長戦略、その勝算に迫る。
東日本大震災から4年が経ち、被災地への関心は、震災直後に比べて格段に風化しつつある。一方で、沿岸部や福島を中心に、復興に向けた課題は多く残されており、道のりはまだ半ばにある。「地方創生の最先端モデルを、東北から」--東北ならではの地域資源を活用した持続可能な取組に向けて、現地ではプレイヤーが立ち上がり、大企業とのコラボレーションや自治体と・中央省庁との人的交流など、新たなモデルが生まれている。震災前の元に戻すのではなく、東北に新たな価値を創出するために、私たちにできることは何か。地域ならではの強みを活かし、新たなイノベーションを生み出すモデルを考える。
2015年2月のダボス会議で、「スポーツ文化ダボス会議」(仮称)を2016年秋に日本で開催することが合意された。文化芸術の担い手やアスリートなど約2000人が世界から集まる。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてムーブメントをつくり、スポーツや文化芸術を通じて、日本の魅力を世界に発信していくために、どのようなアイディアを実現していくべきか。スポーツと文化の祭典の成功に向けて、G1メンバーが議論する。
食やファッション、伝統文化、建築など、日本固有の美意識に育まれたコンテンツは、国内のみならず、海外でも高い人気を博している。2013年には官民ファンド・クールジャパン機構が発足し、食やファッション、ライフスタイルなど、日本の魅力の事業化と海外発信に取り組んできた。池坊次期家元の池坊由紀氏、クールジャパン有識者メンバーを務める生駒芳子氏、国内外で不動の人気を誇る日本酒「獺祭」を手掛ける桜井博志氏、ビエンナーレ国際建築展で金獅子賞を受賞した藤本壮介氏をパネリストに招き、クールジャパン戦略の次の一手を考える。
中国による領空・領海侵犯、東シナ海における防空識別圏設定、北朝鮮核問題といった地政学的リスクの増大に伴い、日本の安全保障環境は厳しさを増している。その中、昨年7月には集団的自衛権行使が閣議決定され、今年に入り、ISILによる日本人人質殺害を受け、自衛隊による邦人救出に向けた法整備が検討されている。世界のパワーバランスが急激に変化し、国際テロやサイバー攻撃といった国境を超える脅威が増大する中で、「積極的平和主義」に基づき同盟国と連携し、国家の安全保障を実現していくために、安全保障法制がどうあるべきかを議論する。
2000年に78.1兆円であった社会保障給付費用は、2014年度には115.2兆円にのぼり、財政の大きな圧迫要因となっている。少子高齢化が進み、社会保険料の収入が低下し、医療費の増大が予測され、社会保障給付費と社会保険料収入の差額は毎年1兆円規模で増大していくと試算されている。社会保障と税の一体改革は、果たして実現できるのか。塩崎厚生労働大臣をゲストに迎えて徹底的に議論する。
ロボット技術の進化は目覚ましく、医療・福祉や建設をはじめ、人手不足に悩む各分野での活用が進み、生産性向上を実現する切り札として注目される。政府は、ロボットによる新たな産業革命を掲げ、技術開発や規制緩和、標準化によって、2020年までにロボット市場を製造分野で2倍、非製造分野で20倍の拡大を目指す。装着型ロボット「HAL」を製造するサイバーダインは、昨年末にオムロンとの提携を発表し、生産革命の実現を図る。ロボットは今後、どのように進化していくのか。生活はどのように変わるのか。サイバーダイン山海社長が描くロボットの未来。
G1サミットから立ちあがった「100の行動」プロジェクト。広く議論を喚起しながら一つ一つ実行に移していくことが狙いだ。独裁政権を打倒する「蜂起による革命」ではなくて、まさに民主主義的な「静かなる革命」である。本ワークショップでは、テーマ毎に小グループに分かれて、「100の行動」の各項目を議論し、具体的な「行動」を提案する。
各グループで議論された「行動」を、1チーム2分で発表してもらい、G1政策研究所のアドバイザーと世耕官房副長官とにコメントしてもらいながら、具体的な行動へと昇華させていく。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2015年03月19日(木)〜2015年03月22日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
2012年末に発足した安倍内閣は、大胆な金融政策と財政政策を矢継ぎ早に打ち出し、日本経済は明るさを取り戻しつつある。持続的な景気回復を実現するには、「第三の矢」である成長戦略の加速的な実行が急務となっている。多様な領域で規制を緩和し、既得権益の岩盤を打ち破り、「成長による富の創出」を実現するために、G1のメンバーたちが取るべき行動とは何か。産業競争力会議メンバー、内閣府副大臣ら安倍内閣のキーマンたちを迎え、今後の方向性を議論する。
中国による東シナ海の防空識別圏設定、歴史認識や領土問題を巡る中韓と日本の外交--東アジア外交の趨勢に、国際社会が注視している。アジアの平和に向けて、日本はどのような役割を果たしていくべきだろうか。外交・安全保障政策において、とるべき道とは何か。尖閣諸島を擁する石垣市で議論するこれからの外交防衛政策。
地域の競争力向上は、安倍政権の成長戦略のひとつに掲げられ、東京一極集中の地域構造から、多様な地域経営への転換が進んでいる。全国の自治体経営の現場では、世代交代と同時多発的な変革が起こりつつある。地域から始まる変革の取組みは、この国をどのように変えていくのか。自治体経営の現場で今、何が起こっているのか。G1サミットから始まった10県知事11市長によるイニシアティブ「G1首長ネットワーク」。産業・IT・教育・少子化対策--同時多発的な変革を通じて、地域から日本を変える取組みを語る。
現代アートの聖地として、国内外から観光客が訪れる直島。2010年に始まった瀬戸内国際芸術祭では、過去2回の開催で、来場者数は200万人を超えた。現代アートは、過疎地をどのように再生したのか。社会をどのように変革する力を持つのか。瀬戸内国際芸術祭の総合プロデューサーを務める福武總一郎氏、同芸術祭の総合ディレクターである北川フラム氏、若手アーティストの旗手として、MITメディアラボ助教に就任したスプツニ子!氏を迎え、現代アートと社会変革について議論する。
全国でいちはやく、全県立高校にタブレット導入を決め、積極的な教育改革を進める佐賀県。佐賀県武雄市では、国内自治体として初めて、小中学生に一台ずつタブレットを配布し、「反転授業」導入に取り組む。ICT活用と民間ノウハウ導入によって、家庭での予習と学校での授業を「反転」するこの試みは、明治時代以来続いてきた日本の教育を変革するのか。下村博文文科相、都内初の民間人校長を務め、全国の自治体教育改革に奔走する藤原和博氏、「生きる力を育てる」独自の学習法で話題の花まる学習会 高濱正伸氏、昨年のG1サミットでも大きな話題となった武雄市図書館をはじめ、公共政策の大胆な改革を進める樋渡啓祐氏をパネリストに迎え、現在進行形の教育革命を議論する。
国家戦略特区は、既得権益の岩盤を打ち破るドリルの刃となり得るか。戦後から数十年間、温存されてきた多くの産業規制は、その役割を果たした後も、既得権益として残り、日本経済の長引く停滞の要因となっている。農業、医療、エネルギー、雇用--これまで聖域とされてきた領域を見直し、競争力ある産業をつくり出していくために、取るべき打ち手とは何か。産業競争力会議メンバー、規制改革会議委員らが議論する。
サービス開始からわずか2年半でユーザー3億人を超えたLINE。利用者の8割を海外ユーザーが占め、台湾、タイ、インドネシアはじめとする東南アジア、そして欧米での市場拡大を図る。海外戦略を積極的に進め、国内では新サービス「マンガボックス」がわずか3か月で累計300万ダウンロードを超えたDeNA。月間1500万人の利用者を誇り、2013年には海外向けサービスを開始したクックパッド。国内外の市場を席巻する話題のベンチャー経営者たちをパネリストに迎え、海外展開とプラットフォーム戦略の次の一手を聞く。
G1サミットから立ち上がった超党派国会議員による「G1政治部会」。昨年のサミットで発表された5つの行動宣言の検証を行うと共に、新たな行動に向けて議論する。「ネット選挙」を機能させる具体的な次の一手とはなにか。外交日程や内政を優先する国会審議をどのように実現するか。政党のあり方と人材確保・育成の仕組みづくりとは。G1に集う政治家たちが与野党の壁を超え、各界のリーダーを巻き込みながら徹底議論する。
新たな日本の地域をつくるために、各地でアートに取り組む人々がいる。文化・芸術による地域づくりが、各地で同時多発的に進められている。別府現代美術フェスティバル「混浴温泉世界」総合プロデューサーである山出淳也氏をプレゼンターに迎え、現在進行形の「アートと地域づくり」の取組みを聞く。
2012年9月、日本中が沸き立った。2020年東京オリンピック開催が決定。五輪担当相に就任した下村大臣は「明治維新、終戦に続く、第三の変革期として新しい日本の創造に向けて取り組む」と語る。世界のトップアスリートが集う祭典に向けて、選手強化はもちろんのこと、都市計画や観光、海外発信、外交をはじめとする様々な課題がある。アスリート・経営者・政治家たちは、どのように連携し、行動していくべきか。2020年に向けたマイルストーンと「五輪後」の日本を議論する。
成長戦略の一環として、官民連携ファンドの創設・機能拡充が進められている。官民連携ならではの投資インパクトを持ち、長期的視点に立った産業育成と民間投資の活性化を実現するために、ファンドに求められる戦略とは何か。ジャパンディスプレイへの大型出資をはじめ積極的な投資を行い、国内業界の再編・育成を推進する産業革新機構のCOO、日本ブランドの発信を目的に、2013年11月に設立されたクールジャパン機構のCIOらをパネリストに迎え、国際競争力を持つビジネスモデルの実現に向けて議論する。
安倍内閣は「女性が輝く日本」を掲げ、成長戦略の一環として「待機児童の解消」「職場復帰・再就職の支援」と共に、「女性役員・管理職の増加」を推進する。一方で、日本の上場企業の女性取締役比率は1.2%と、政権の掲げる「女性役員を上場企業に1人」実現に向けた道のりは遠い。企業経営の現場で「女性が輝く社会」を実現するために、政財学界のリーダーたちはどのような行動に取り組むべきか。内閣府特命担当大臣として少子化対策・男女共同参画に取り組む森雅子氏を迎え、G1サミットから生まれたダイバーシティ・イニシアティブのメンバーたちが議論する。
世界最大のPR会社エデルマンの昨年の調査によれば、日本人のメディアへの信頼度は、他国と比較して下位レベルだという。ソーシャルメディアやインターネット動画が普及し、情報発信や供給の形態が変遷する中で、既存メディアは生き残れるのか。メディアは今後、どのような役割を果たしていくべきか。G1メディア部会が策定する、日本のメディア変革に向けた行動宣言。
新たな日本の地域をつくるために、各地でアートに取り組む人々がいる。文化・芸術による地域づくりが、各地で同時多発的に進められている。八戸ポータルミュージアム「はっち」オープニング事業を担当した吉川由美氏を現在進行形の「アートと地域づくり」の取組みを聞く。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2014年03月20日(木)〜2014年03月23日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
2012年12月26日、第二次安倍内閣が発足した。第3回G1サミットのゲストである安倍晋三氏を筆頭に、小野寺五典防衛大臣、林芳正農林水産大臣、柴山昌彦総務副大臣、西村康稔内閣府副大臣、平将明経済産業大臣政務官兼内閣府大臣政務官、丸川珠代厚生労働大臣政務官、義家弘介文部科学大臣政務官ら、多くのG1メンバーが入閣し、国政の指揮に当たっている。もはや一刻の猶予もならない中、この国の再生に向けて、我々は今、何をするべきだろうか。党派・領域を超えて、G1メンバーとして取るべき行動と連携を問う。
終身雇用神話が崩壊し、採用システムが硬直化する一方で、企業の枠から離れたところで、新たな「起業」スタイルを選ぶ個人が現れ始めた。ワークシフトする世界において、地域・国境を軽々と飛び越え、雇用/非雇用や上場/非上場の枠組みにさえ捉われず、彼らが選ぶのは「やりがい」「自由」「人とのつながり」--。企業一社が永続的な雇用の受け皿となり得ない時代において、突き抜けた人材としての「個」を輩出し、イノベーションの生態系をつくるために、これから必要な社会資本とは何か。脳科学者の茂木健一郎氏、「若者論」で注目される古市憲寿氏、若手起業家を代表する岩瀬大輔氏が語る「イノベーションの新たな生態系」。
第二次安倍内閣は、「経済の再生」を政権の使命と掲げ、強い経済を取り戻すために、大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして規制緩和と投資促進を通じた成長戦略の重要性を打ち出した。過去10年以上のデフレから脱却し、イノベーションと事業創造を通じて、「成長による富の創出」を実現するために、いま必要な成長戦略とは何か。国としてどの領域に注力し、企業の闊達な経済活動を支えていくべきか。企業経営者はどのようなイニシアティブをとるべきか。経済産業大臣政務官、産業競争力会議メンバーらをパネリストに迎えて議論する日本の「新・成長戦略」。
Twitter、Facebook、YouTube、ニコニコ動画をはじめとするソーシャルメディアは、政治家と有権者を直接結びつけ、その活動を可視化するツールとして、もはや欠かせない存在となっている。ウェブは政治を変え得るか。安倍内閣が掲げるネット選挙解禁は、旧来の世代間格差・地域格差を打破する打ち手となり得るのだろうか。ウェブが政治にもたらす「新たな民主主義」と実現に向けた道のりを議論する。
日本の再生に向けて、高度成長時代とは異なる新しい社会の枠組みが求められている。超少子高齢化社会を前に、労働力確保に向けた政策が議論される中、女性を労働力として活用することは、企業の競争力向上、税政確保の両面において、益々その重要性を増している。一方、現状では、長期に亘る女性の教育投資の回収ができておらず、先進国の中で最低水準のジェンダーギャップに甘んじている。新たな社会の枠組みの礎となる価値観を創造し、意識変革を実現するために、G1メンバーとして何をするべきか。前回G1サミットで生まれたダイバーシティ・イニシアティブメンバーが行動宣言する。
日本の音楽シーンはなぜK-POPにここまで押されてしまったのか。日本のエンターテイメント界が世界で勝つための戦略とは。10年以上にわたりJ-POPを牽引してきた「ハロー!プロジェクト」の総合プロデューサー、つんく♂氏が現状を紐解きながら、リズムで日本を元気にする可能性について語ります。つんく♂氏プロデュースのボーカルユニット、THEポッシボーによるショーもお楽しみ下さい。
製造業をはじめとする日本の重厚長大産業が低成長に喘ぐ一方で、多くの新興企業が、めざましい成長を遂げている。NHNジャパンが立ち上げたLINEはこの1月18日、サービス開始からわずか1年7ヵ月で、ユーザー数が1億人の大台に上った。日本のみならず東南アジア諸国、南米でも多くのユーザーを獲得し、さらなるグローバル展開を強化する。DeNAの4~9月営業利益は、前年同期比30%増の388億円。12月には米国GooglePlayの売上ランキング上位3位をMobageタイトルが占める等、海外でもMobageの成長が目に見える形になってきた。縮小する市場を競うのではなく、新たなサービスを創出し、世界で活躍する企業の共通点を探ると共に、"世界に突き抜ける”メガベンチャー輩出に向けて、必要な打ち手を議論する。
まずは投資家に好感をもって迎えられたアベノミクス。今後、市場はアベノミクスに何を期待し、何を恐れるのか。金融緩和効果とハイパーインフレ、公共投資による景気浮揚と財政バランス、円安のメリットとデメリットなど、エコノミスト、株式、債券の専門家が、市場という観点から、成長を促進維持する為のあるべき金融財政政策を議論する。
自治体経営における「選択と集中」が進む中、民間企業やNPOとの連携・業務委託による経営効率化は、収支改善のみならず、住民サービス向上面においても、重要な戦略となっている。多様化する住民のニーズに応え、高い付加価値を生み出していくために、自治体と企業は、どのようなコラボレーションを実現していけるのか。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営受託し、2013年4月にリニューアルオープンする「武雄市図書館」は、蔵書数20万冊、年中無休とし、開館時間を9時から21時に拡大を予定している。「新しい図書館のロールモデル」を目指す同図書館の事例から、企業が公共で果たす役割を議論する。
自動車をはじめとする日本製品への信頼感、ゲームやアニメへの圧倒的支持、食やファッション、建築への国際的評価など多くの優れたアセットを持ちながらも、国としての発信力を長く持たないままにきた。ダボス会議に代表される国際会議における日本のプレゼンスも低下した今、発信力を競争優位につなげるために、取るべき行動とは何か。G1サミットから始まったクール・ジャパン・イニシアティブの中心メンバーたちと、戦略コミュニケーションの専門家が、日本の発信力強化に向けた行動宣言を行う。
G1サミットから、多くのイニシアティブが生まれている。スポーツ界の変革を目指す「アスリートソサエティ」、クール・ジャパン官民有識者会議を中心とする「Cool Japanイニシアティブ」、東北と日本の食を世界に発信する「東の食の会」、被災地の復興支援を目的とする「KIBOW」、被災地を共に走って支援する「トライアスロン・イニシアティブ」――。G1から生まれたプランと連携は、業界や領域を超えて、社会を変革する原動力となっている。今回のワークショップでは、新たなテーマを加え、社会変革に向けて、自分たちが明日から行動できるステップを14の領域で議論する。
世界で初めて小惑星の微粒子を地球に持ち帰ることに成功した、小惑星探査機「はやぶさ」。日本人宇宙飛行士の長期滞在を実現した、国際宇宙ステーション内実験棟「きぼう」。日本の宇宙開発事業が大きな成果を上げ、宇宙開発利用の果たす役割が国際的に益々拡大している。一方、2013年からの次期宇宙基本計画では、予算減額・2020年の月探査目標撤回が検討されている。資源開発・安全保障・外交・人材教育、多様な点を踏まえ、国として目指すべき宇宙開発のあり方を、参加者と共に考える。
古来、日本人は、花鳥風月の世界に暮らし、自然を愛でる眼差しに溢れていた。しかし、現代の日本では、こうした自然の美しさに触れる機会も減り、その心を忘れがちである。日本美術に表現された価値観や心は現代の私たち日本人だけでなく世界に訴えかける普遍性を持っている。今回のセッションは、ニューヨークを拠点に活躍し、作品を通してその心を表現し続けるアーティストの一人、日本画家・千住博氏と、日本初の日本画専門美術館の三代目館長の山﨑妙子氏をお迎えする。二人の対談を通して、日本美術と出会い、日本人としてのアイデンティティ、生き方に新たな視点をもたらすきっかけとなるのではないだろうか。
2011年3月、福島第一原子力発電所で起きた事故は、日本のエネルギー政策を根底から揺るがした。国内原子力発電所54基中52基が稼働停止し、液化天然ガスの輸入額は21.8兆円に上り、貿易収支の圧迫要因となっている。エネルギー価格の上昇は製造業のコストを圧迫し、企業の海外移転を促進させている。安全面を重視しながらも、安価で安定的なエネルギーをどのように確保するのか。安全保障・外交・環境問題を視野に入れ、社会的コストを最小化する日本のエネルギー政策のあり方を議論する。
2012年9月、7県知事11市長が参画する「G1首長ネットワーク」が結成された。同年12月に行われた合宿では、全国の改革派首長が、立場を超えて議論し、「同時多発的な行動」を仕掛けていく事を確認した。首長達が、G1ネットワークを活かして同時多発的に実施する行動とは何か。日本の未来を拓く「行動宣言」をこの場で発表し、参加者と共に議論する。
東日本大震災から間もなく2年を迎える。震災の爪痕はなお深く、インフラ復旧、農林漁業や製造業の復興、雇用創出など、課題はなお山積みとなっている。一日も早い復興に向けて、政府・行政と企業・NPOや研究機関が一体となって、具体的な道筋を描き、実行していく必要がある。第二次安倍政権で復興副大臣に就任した浜田昌良氏、民主党政権時から福島復興に並みならぬ尽力を続ける細野豪志氏、震災後いち早く会津若松にアクセンチュア 福島イノベーションセンターを創設し、東北の産業振興・雇用創出を推進する程近智氏をパネリストに迎え、復興に向けてG1メンバーが取るべき行動を議論する。
国際社会において担うべき未来像を考える時、我々は自ずと、日本のアイデンティティと国のありようを自問する。何を国の礎とし、どのような国づくりを目指すのか。歴史や美徳、公を重んじる価値観--連綿と育んできた文化を、普遍的な価値に昇華し、世界に貢献していく国をつくるために、取るべき行動を議論する。
国境を越えた人材の往来が加速化する中、大学経営の国際競争は、さらに熾烈を極めている。世界中から優秀な学生を集め、知の基盤を確立し、卓越したリーダーを輩出することは、国としての競争力強化に直結する。一方、東京大学が進めてきた秋入学には、立ちはだかる障害も大きく、変革に向けて多くの課題が残されている。社会変革を実現する「大学改革」のあり方を問う。
2012年ロンドンオリンピックで日本は、史上最多となる38のメダルを獲得した。世界で活躍するアスリートたちの姿、気迫や覚悟は、見る者の心を揺さぶり、深い感動を与える。北島康介氏、為末大氏、古田敦也氏――水泳、陸上、野球のトップアスリートが集い、日本のスポーツが世界で勝つためにできること、教育やコミュニティ形成に向けてできることを議論する。
G1サミットに参加した33名の国会議員で構成する「G1政治部会」が、前回のG1サミット後に発足した。「党派や立場を超えて、新たな政治を実現していくために何をするべきか」、を1年間かけて議論してきた。田嶋要氏のリードのもと、菅政権で内閣官房副長官を務めた福山哲郎氏、現内閣官房副長官の世耕弘成氏、みんなの党政策調査会長の浅尾慶一郎氏らが、日本の政治を良くするための、5つの行動宣言を発表し、参加者と議論する。
日本の領土問題に関する事件が頻発し、近隣国との摩擦要因となっている。ロシアとの間の北方領土、韓国との間の竹島、そして特に、近年軍事力の増加が著しい中国との尖閣諸島を巡る緊張は、日本の防衛・安全保障政策における領土保全の重要性を、改めて国民に知らしめることとなった。領海・領空侵犯が相次ぐ中で、国家主権の根幹を成す領土・領海権の問題に、我々はどのように立ち向かうべきか。
2012年、日本と中国では新たな指導者が生まれ、米国ではオバマ政権が2期目を迎えた。日米中における相対的力学は、過去20年ほどの間に大きく変化したが、新たな体制の下で、各国はどのような外交政策を展開していくのだろうか。オバマ政権が掲げた「アジアへの回帰」政策は、中国そして日本にとってどのような意味を持つのか。オバマの米国と習近平の中国は、どのようなパートナーシップを目指すのか。三国が新たな相互関係を迎え、東アジアの力学が変わる中、日本が取るべき外交戦略を議論する。
2012年には新規国内LCC(格安航空会社)3社が運航を開始、LCC元年となった。また同年3月には「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案」が閣議決定され、「空の自由化」に向けて急速に舵を切っている。LCCは、地域活性化の起爆剤となり得るか。一連の規制緩和を、国内外からの観光客誘致・地域活性化につなげるためには、航空会社と空港、自治体をはじめ、各プレイヤーが一体となった経営努力が求められている。空の自由化を、地域の価値向上と強い産業創出につなげるために必要な打ち手を、LCC・観光・自治体を代表するパネリストが議論する。
政治への信頼が揺らぐ中、世論形成を担うべきメディアにも様々な批判の声が向けられている。新しい世論の担い手として、ブログやソーシャルメディアも登場しているが、既存メディアが持つ影響力にはいまだに大きなものがある。ソーシャル時代に我々はメディアをどう活用すべきか、またメディアの使命とは何なのか、新聞、テレビ、雑誌、ネットメディアなどの最前線で働くプロを招き、日本をよくするためのメディアの役割について議論する。
企業が社会的問題の解決に取り組み、NPOが持続可能なセクターを目指す中、事業を通じて社会問題を解決する「社会起業家」の役割は、一層拡大している。企業やNPO、行政の連携に、社会起業家はどのようなイニシアティブを取るべきか。持続可能なモデルを構築し、より大きなインパクトを実現するために、必要な行動とは何か。公益の実現に向けた5つの行動宣言。
「批判よりも提案を」「思想から行動へ」--G1サミットの行動指針に則り、過去4回のG1サミットから、多くの部会・イニシアティブが生まれた。今回のG1では、新たに5つのテーマで「行動宣言」が実施された。政治、首長、女性の活用、日本の発信力、そしてソーシャル・アントレプレナーシップである。最後の全体会では、各テーマのリーダーをパネリストに迎え、G1メンバー各人が、どのように行動し、社会を変革するのかを議論する。「G1サミット発の行動が、日本を変える!」。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2013年02月08日(金)〜2013年02月11日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
2010年に政府の掲げた新成長戦略では、「観光立国・地域活性化戦略」を4つの成長分野のひとつに掲げ、訪日外国人旅行者数を「2020年までに2500万人」と掲げた。しかし、3月11日の東日本大震災とその後の一連の事故によって、2011年の訪日外国人旅行者数は、前年同期比24.4%減の714万人と大幅に縮小し、観光業界が甚大な打撃を受けるのみならず、国の成長戦略も見直しを余儀なくされている。3.11後の観光立国ヴィジョンを新たにどう描くのか。近隣諸国の富裕層拡大を視野に、どのような戦略転換を図るべきか。観光の論客が語る「新・観光立国」戦略。
超少子高齢化社会を前に、移民をはじめとして、労働力確保に向けた政策が活発に議論されている。日本の女性労働力率をOECD平均並に引き上げれば、それだけでGDPが16%上がるという試算もある一方、世界経済フォーラムによる「ジェンダーギャップレポート」では、日本は135カ国中98位と、先進国の中で最低水準となっている。女性がいっそう活躍する社会をつくるために必要なことは何か。世界経済会議(WEF)の女性評議会の男性委員がモデレートし、各界で活躍する女性リーダーたちが議論する。
明治初期、新たな国づくりを夢見て、渋沢栄一が第一国立銀行を設立した時に、日本の資本主義は、その幕を開けた。それから百数十年、米国型資本主義の席巻、バブル崩壊、リーマンショックを経て、世界は新たな資本主義の形を模索している。日本の近代資本主義とは何であったか。それは変わりゆくものなのか。変わらざる価値観とは何か。過去から受け継いだ歴史と道徳を母胎として、日本は新たな資本主義を生み出し、世界に発信してゆけるのではないか。渋沢栄一翁の五代目の子孫である澁澤健氏、日本型資本主義の第一人者である田坂広志氏による近代資本主義の振り返りと新たな価値観を育む対話の場。
インターネットの技術革新は、黎明期から普及期を過ぎ、今や社会システムを根底から変える新たな段階へと足を踏み入れた。ソーシャルメディアの普及は、世論形成の過程を根底から変えようとしている。情報、データやソフトウェアは今や、ネットを通じて「あちら側」の世界に置かれるものとなりつつある。ソーシャルメディアとクラウドは今後、どのようにコミュニティを変え、ライフスタイルを変え、情報のあり方を変えていくのか。ネットベンチャーの新たな旗手が語る。
東日本大震災と巨大原発事故は、震災から1年経とうとする現在になっても東北地方の食に深刻な風評被害をもたらしている。情報が錯綜する中、安心・安全の体制を確立し、正しい情報を発信するために、生産者・政治・行政・企業・消費者はするべきことは何か。前回のG1サミットを契機に設立された一般社団法人東の食の会の活動紹介と共に、食のキーパーソンたちが議論する。
韓国企業が、ウォン安・FTA・低法人税の比較優位を活用し、自国製造拠点を足場に世界を視野に展開を図る中、日本の製造業は、円高・法人税・電力問題等の6重苦に喘いでいる。中国・インド・中南米・中東をはじめとする新興国市場が拡大する中、日本の製造業が取るべき新たな戦略とは何か。日本の製造業に詳しいアナリスト、経営者が議論する。
2007年の参院選挙から現在までほとんどの期間、国会は「ねじれ」の状態にある。短命政権が続く最大の要因として「ねじれ」が挙げられることも多い。税と社会保障の一体改革、TPP、東北復興をはじめとする重要議案が山積みの中、内閣・与野党は「ねじれ」国会にどのように対応していくべきか。世界情勢の混迷が続く中、政治が強いリーダーシップを実現していくために、国会制度・運営のあるべき姿とは何か。気鋭の政治家たちが議論する。
政府が医療費削減を目指す一方、医師不足への対応、救急・地域医療体制の増強医療・創薬技術の開発投資が急務となっている。医療システムの問題の本質とは何か。医療費削減と医療の質向上を両立する第三の道はあり得るのか。コストではなく、社会成長の基盤投資としての医療を考える時、我々はどのような医療を目指すのか。そこには、どのような可能性が広がっているのだろうか。病院・医薬企業・政治家のキーパーソンたちが語る成長戦略としての医療改革。
World Economic Forum(世界経済フォーラム)のYoung Global Leadersが中心となって立ち上がった2つのイニシアティブ。東日本大震災で被災した若者たちへのリーダーシップ支援を目的として創設された「Beyond Tomorrow」。世界の「食」の不均衡を解消するため、先進国と開発途上国で食事を分かち合うための「TABLE FOR TWO(二人の食卓)」。2つのイニシアティブの取組みを通じて、日本の再創造と世界貢献を考えるランチセッション。 (*今回のヘルシーランチの費用の一部が、TABLE FOR TWOを通じて開発途上国ならびに東北被災地に届けられます)
世界のパワーバランスと価値観が大きく変化しつつある中、日本は、長引く経済低迷、社会保障の負担増大に喘ぎ、明確な打ち手を見出せないまま、その優位性を失いつつある。日本は今、どのような国づくりのヴィジョンを共有し、どのように行動していくべきだろうか。閉塞感を打破し、新たな時代を切り開くための政治はどのようにあるべきか。今後の日本を担う政治のリーダーたちが議論する。
2020年、我々はどのような国を目のあたりにするのだろうか。「優雅な衰退」という名の衰亡を遂げた国か。変革と再生の痛みを経て、再び繁栄と成長を手にした国か。岐路に立った日本は、どのような国づくりのヴィジョンを共有し、行動していくべきか。日本の進むべき道とリーダーの取るべき行動を問う。
エネルギー政策の揺らぎは、日本の競争力の弱体化に直結する。原発再稼働の方針を掲げた政府だが、ストレステストと地元同意のハードルの前に、未だその具体的な道筋を示せずにいる。その間、燃料費の輸入増に伴い貿易赤字が続き、産業の空洞化も進展している。一方、管野飯館村長やその地域に住む避難民にとっては、故郷への帰還は、一刻も早く実現したい悲願である。原発問題の責任者である細野大臣を迎え、原発再稼働と避難民帰還への道筋を討議する。
2011年11月、野田内閣は環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加に向けた協議に入ることを表明した。韓国等にFTA競争で出遅れている中、TPP参加は、日本の産業強化の推進力となり得るのか。また、農業は本当にTPPの犠牲となってしまうのか。現役のWTO幹部、政治家、農業従事者が、竹中平蔵氏のモデレートのもと、TPP交渉参加の意義を議論する。
3月11日に宮城県沖を襲った東日本大震災は、東北沿岸を中心に甚大な被害をもたらし、自然風土の凄まじい力と人間文明の非力さを見せつけた。それは同時に、縄文の昔から豊穣を蓄積してきた東北の恵みの豊かさ、地域の絆の確かさ、そして中央政権に対する「辺境」としての東北を人々に再認識させることとなった。東北で何が起こったのか。無数の慟哭から、我々は何を学んだのだろうか。「東北学」の父であり、東日本復興構想会議委員である赤坂憲雄氏が語る東北のもうひとつの歴史、鎮魂と再生に向けた道のり。
東日本大震災による被害は、農業・漁業、製造業、観光業をはじめ地域の産業に大きな爪痕を残した。震災からの地域の再生を加速するために、骨太な戦略とその実現が急務だ。産業・雇用とコミュニティを再創造し、次世代が希望を持って暮らせる地域社会を創るために、政・官・民は何をするべきか。復興予算はどのように未来へと投資されるべきか。復興の中核を担うリーダーたちが、その戦略と実行について議論する。
昨年末に開催されたCOP17は、「ダーバン合意」採択によって閉幕した。この採択により、2020年には米国や中国を含むすべての国が参加し、気候変動に対する新たな枠組みが開始される。気候変動分野で、日本の立ち位置はどうあるべきなのか。世界の主要国は、本当にまとまるのか。2020年段階での25%削減目標の公約をどう考えるのか。昨年末にダーバン入りした政財界を代表する環境戦略のキーパーソンたちが、ダーバン会議での議論を振り返り、今後とるべき環境戦略を議論する。
京都大学の山中伸弥教授らが、世界に先駆けて樹立したiPS細胞は、難病のメカニズムの解明、再生医療への道を示すと共に、人類の生命や遺伝子の謎を解き明かす手掛かりとして、世界中から大きな注目を集めている。一方で、臨床研究に向けた道のりは長く、激しい国際競争が続いている。日本のiPS細胞技術が世界に普及し、臨床分野で羽ばたく日を目指して、政学官民の立場を超えたチーム・オールジャパン戦略を考える。
知性とは何か。太古から人は言語を生み、火を使い、森羅万象の中に法則性を見出すことによって進歩を遂げてきた。闇の深淵に何があるのかという畏怖と探求心は、宗教を生み出し、天文学をつくり、ロケットを発明した。見えないものを見ようとする知性は、新たな世界観を育み、世界を変革する力となって、人類をいまだ知らざる土地へと連れて行く。宇宙を回遊し、インターネットでつながれた情報の海を泳ぎながら、現代における知性は、どのような世界を夢想するのだろうか。脳科学者の茂木健一郎氏が語る知性とは。
今や時価総額世界5位に駆け上がったGoogleの事業展開は、各国の法的リスクとの戦いの軌跡でもあった。技術革新や活気的なビジネスモデルが、人々の行動や価値観さえ根底から変えていく時代において、企業のコンプライアンスのあり方は、どのように変化していくのか。市場への信頼を担保しながら、たえまないイノベーションを実現していくために、どのような企業統治を考えるべきだろうか。
2011年夏、産業革新機構と東芝によるスマートメーター最大手への出資が大きく報じられた。産業再生機構によるカネボウやダイエー、九州産業交通の再生は記憶に新しく、現在は、企業再生支援機構のもと、日本航空が再上場に向け、再建を進めている。長期的視野に立った企業再生、産業構造やビジネスモデルの変革は、どのような戦略と組織から生み出されてきたのか。次世代の国富を担う産業創出に向けて、どのような可能性を秘めているのか。産業再生機構OB、産業革新機構COOらが語る。
ソーシャルメディアの普及に伴い、情報は一部のマスメディアが独占して発信するものから、個が発信しインターネットを通して伝播していくものへと変質した。アラブの春ではツイッターやFacebookが大きな役割を担った。日本でも、3.11を機に日本の官邸や官公庁もツイッター導入に踏み切り、多くの政治家がニコニコ動画で会見を行うようになっている。だがインターネットを選挙活動に使えない現況では、ソーシャルメディアが本当に政治を変え得る位置にあるのかは、まだ見えない。ソーシャルメディアが生み出す新たな政治の形とはどのようなものか。メディアの第一人者たちが議論する。
2011年3月11日をきっかけに、日本の発信力についての問題意識がかつてないほどに高まっている。震災直後の日本人の行動は、多くの海外メディアから賞賛された一方、原発事故を巡る情報の不足・錯綜は、国内外に多くの混乱を招き、観光や食品輸出に甚大な影響を与えた。危機管理力としてのコミュニケーション戦略を問う。
ギリシャ財政危機に端を発した欧州金融危機は、ユーロ加盟国のみならず、今や世界経済全体のリスク要因となりつつある。ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインの財政不安を抱えながら、「ひとつの欧州」は継続し得るのか。欧州のフランスを含む主要国の格付けが、一斉に格下げされた。本当にユーロ破綻のシナリオはあり得るのか。その時、米英・新興国はどのように影響を受けるのか。ユーロ危機の趨勢と世界経済に与える影響を考える。
日本の一般歳出に占める社会保障費の割合は、今や5割を超えるに至った。社会保障費の多くは将来世代へと先送りされ、少子化の進行と共に現役世代の負担は拡大し、世代間格差の大きな要因となりつつある。社会保障費が年1兆円規模で拡大する中、消費税10%への引き上げのみで、財政健全化と社会保障維持の両立は可能なのか。経済の負担をどう考えるか。「税と社会保障の一体改革」は、少子高齢化に向かうこの国の財政と社会保障問題を、経済の犠牲無しに解決できるのか。2020年までの基礎的財政収支黒字化に向けたマイルストーンと社会保障のあるべき姿を問う。
中国の経済的、外交的、軍事的台頭とは対照的に、政治の不安定、外交戦略の欠如、経済の低迷から国際社会で存在感が低下し続ける日本。一方、米国オバマ政権は「アジア重視」の姿勢を打ち出しつつ、日本や韓国、インド、ASEANとの協力強化を推進し、中国の動きを牽制している。変化する東アジア情勢を背景に、日本は東シナ海問題等をめぐって緊迫した関係にある中国とどのように付き合うべきか。日本外交が取るべき指針とは。
3月11日の東日本大震災直後、情報が錯綜しインフラが遮断される中、NPOやボランティアが立ち上がり、救援物資を届け、捜索や瓦礫処理を続けた。多くの企業が寄付を決め、サプライチェーンの迅速な回復は、復旧の大きな足掛かりとなった。震災直後から被災地で、生活・教育支援、町づくりやファンドレイジングに邁進するリーダーたちが、復興の希望-KIBOW-に向けた取組みと思いを語る。
雇用や社会保障における世代間格差が指摘され、若年層に閉塞感が広がる一方で、財政界を中心に、静かな世代交代が進み、新たな変革の旗手たちが出現している。既得権益からの権力奪取、イノベーションの実現、新たな価値観の創出。36歳で全国最年少現職知事として当選した鈴木知事、33歳で史上最年少の東証一部上場を果たした田中氏、25歳で七大陸最高峰の世界最年少登頂記録を更新したアルピニストの野口氏に、日本再創造に取り組む1970年代生のリーダーたちの取組みを聞くとともに、G1サミットのリーダー達に望むことを語ってもらう。
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2012年02月10日(金)〜2012年02月12日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
サントリー白州蒸留所にてディナーをお楽しみいただきます。(※20歳以上の方のみご参加いただけます)「プールサイドディナー(ご家族向け)」
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2011年02月10日(木)〜2011年02月13日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2010年03月19日(金)〜2010年03月22日(月) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |
(プログラムは予告なく変更される場合がございます)
| 日時 | 2009年02月13日(金)〜2009年02月15日(日) |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人G1サミット |







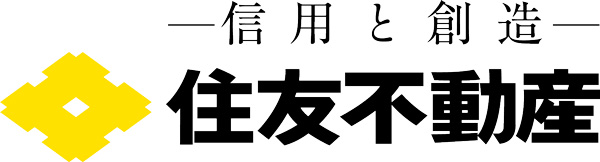





















東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル 株式会社グロービス内
TEL:03-5275-3681 FAX:03-5275-3890
E-Mail:conference@globis.co.jp